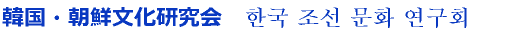![]()
□ 日時:2019年10月26日(土) 10:00~18:00
□ 場所:東北学院大学土樋キャンパス
ホーイ記念館3階304号室(会場)・307号室(控室)
交通アクセス・施設案内
□ プログラム
| 09:30 | 受付開始 |
||||
| 10:00~12:00 | 一般研究発表(司会:辻大和) 水谷清佳「大韓帝国期における妓生をめぐる環境と社会活動」 崔蘭英「『大河内文書』にある第二次修信使との筆談(『韓人筆話』について」 金志善「京城放送局(JODK)の音楽プログラムに関する一考察―1920年代を中心とした各音楽ジャンルの分析から―」 |
||||
| 12:30~12:50 | 会員総会 |
||||
| 13:00~18:00 | シンポジウム「近現代韓国・朝鮮における街頭集会・示威」(企画:月脚達彦、司会:六反田豊) 月脚達彦「趣旨説明:近現代韓国・朝鮮における街頭集会・示威を見る視点」 松谷基和「三一運動における万歳の意義 ─近代的ネイションとしての『朝鮮』の産声」 真鍋祐子「三・一運動からキャンドル集会まで ―─死生観と歴史認識から考える」 18:00~20:00 | | 懇親会 MEINA(イタリア料理) |
仙台市若林区清水小路6−1 東日本不動産仙台ファーストビル 1F 電話022-395-8950 |
□ 一般研究発表
水谷清佳「大韓帝国期における妓生をめぐる環境と社会活動」
「妓生」は高麗時代と朝鮮時代、宮中・地方官庁の各種宴享及び公私行事で呈才や歌舞奏などを担当した伝統的な「芸人」を指す。宮中所属の京妓と地方官庁所属の郷妓で構成された妓生たちは官の『妓籍(または妓案)』に登録され、国家によって「女楽制度」として体系的に管理されていた。
朝鮮開国以降、妓生をめぐる環境は徐々に変化する。京妓は内医院、恵民署、尚衣院、工曹の4部署に配属されていたが、1882年に恵民署、1894年に工曹が廃止された。甲午改革時には公私奴婢の廃止により妓生は賤民の身分から解放されるが、京妓はほぼ妓役を引き継いだ。郷妓は1895~6年にかけて一部地域に限り廃止が進んだものの、1897年頃から郷妓を廃止した地域でも地方教坊の妓生が再生されたことから、大韓帝国期(1897年~1910年)の妓生は太医院(旧内医院)の医女(薬房妓生)及び尚衣司(旧尚衣院)の針線婢(尚房妓生)と郷妓に区別された。
日本と韓国における大韓帝国期の妓生に関する先行研究には、音楽学や舞踊学分野から歌舞奏を取り上げたもの、歴史学分野から妓生制度の変化を取り上げたもの、女性学分野から近代の妓生制度と公娼制度の関連性を取り上げたものなどがある。以上の研究により当時の妓生の芸や生業、制度はある程度明らかになったが、これ以外の妓生の活動を具体的に検討したものはほとんどないと言える。しかし近年、妓生の生業以外の活動すなわち社会活動に注目した研究が本格化し、なかでもファンミヨン(2011年)が先駆的である。これは新聞と関連記録から植民地中期1923年~1934年の妓生の社会活動を民族主義的社会運動の参与、集団性の模索、地位向上の要求、愛国運動の展開の4つのカテゴリーに分類し考察している。また、水谷(2018年)は植民地初期(1908年~1919年頃)における妓生の社会活動を寄付活動、差別する/される妓生集団、愛国活動の3つのカテゴリーに分類し考察した。しかしまだ「官妓」であった大韓帝国期の妓生の社会活動は明らかにされていない。
そこで本発表では、まず大韓帝国期における妓生をめぐる環境の変化を具体的に検討する。そして妓生が「妓生団束令」により解体される前であり、朝鮮の最後の官妓として存在した1897年から1908年までの彼女らの社会活動を『独立新聞』、『皇城新聞』、『帝国新聞』、『大韓毎日申報』、『万歳報』をもとに教育活動、社会的な主張、慈善演奏及び寄付活動、愛国活動の4つのカテゴリーに分類し考察する。以上から大韓帝国期における妓生像と当時の妓生の活動の社会的な意義を明らかにしたい。
崔蘭英「『大河内文書』にある第二次修信使との筆談(『韓人筆話』について」
周知のように、「日朝修好条規」以降に朝鮮の無関税貿易が定められ、朝鮮では貿易が始まった直後からその不平等性が問題視されることとなった。このことについて交渉すべく、1880年7月に金弘集を正使とする第二次修信使が日本に派遣された。日本政府と外務当局の意向を探るほか、「物情詳探」も一行の果たすべき重要な使命であった。訪日中に、金弘集は清の駐日公使館を訪れ、初代公使の何如璋、参賛黄遵憲などと筆談を交わし、黄遵憲から対西洋化開国、開化自強政策をすすめる著書、『朝鮮策略』を贈られて持ち帰った。この『朝鮮策略』は国王、政府に大きな影響をおよぼし、これを機に朝鮮は開国開化政策に転じた。こうした経緯から、従来の第二次修信使に関する研究は『朝鮮策略』に集中し、金弘集一行の日本滞在中の一ヶ月余りの間の行動も、もっぱら清の対朝鮮政策との関連で捉えられてきた。
報告者は日本学術振興会科研費の助成(基盤研究(C)(一般)研究課題番号:17K03142)を受けて、共同研究者である北原スマ子氏とともにいくつかの新しい資料を駆使し、金弘集とその一行が日本に滞在中、具体的にどのような人物と接触し、どのように行動して人脈を形成したのかを考察した(「『近代』移行期の東アジア知識人の人的ネットワークについての基礎研究(三)――第二次修信使金弘集一行の日本滞在を中心に――」常磐大学人間科学部紀要『人間科学』第37巻第1号、2019年9月)。その結果、公式の外交使節として派遣されていた第二次修信使一行は、日本の外務省官僚や清国の公使館館員と往来があるほか、宮島誠一郎や興亜会のメンバーたち、そして源輝声など、日本と清の民間人とも重層的な交流をしていたことが確認できた。
高崎藩藩主であった源輝声(1848~1882)は、廃藩置県以後に政治の場から離れ、華族となったが、黄遵憲をはじめ、多くの清国駐日公使館関係者と交遊し、「大河内文書」と名付けられている大量の筆談資料を遺した。中には、修信使一行との筆談、書信など(1880年8月27日から9月6日まで約10日間)が収録されているが、これまで利用されることがなかった。筆談に参加した朝鮮側の人物は金弘集、李容粛、李祖淵、金允善、卞鐘夔、姜瑋の6人で、対談したのは源輝声のほか、元対馬藩主の宗重正、亀谷省軒、石川鴻齋、清国人の王治本などであった。
本報告はこの筆談集について詳細に検討した結果を報告するものである。第二次修信使の訪日を通して、日本、朝鮮そして清の知識人たちが互いにどのようなことに関心を持ち、どのような会話を展開したか、その交流の実態を明らかにする。
金志善「京城放送局(JODK)の音楽プログラムに関する一考察―1920年代を中心とした各音楽ジャンルの分析から―」
本発表は、植民地朝鮮における京城放送局(JODK)の音楽プログラムについて、1920年代を中心に、朝鮮音楽・日本音楽・西洋音楽・大衆音楽・音楽教育の5つの音楽ジャンルに分けて分析することで、娯楽プログラムの中で圧倒的に多く編成された音楽プログラムの実態を明らかにし、当時のメディアにおいて音楽番組が有していた意義について考察するものである。
京城放送局は1927年2月16日に開局し、「報道」「教養」「慰安」を原則としたプログラムを編成していた。特に「慰安」放送では、音楽プログラムが最も多く編成されており、漫才、ラジオドラマなども盛り込まれていた。社団法人京城放送局は1933年4月7日に朝鮮放送協会に改称し、日本語と朝鮮語の二重放送が始まる前までは、単一放送で日本人向けのプログラムと朝鮮人向けのプログラムが交互に編成されていた。
開局当初から編成されたプログラムについて、先行研究では、植民地支配の道具としての役割が強調され、特に宣伝道具として活用されていたという見解が示されてきた。一方、娯楽プログラムに関しては、国文学分野で主にラジオドラマや放送小説といった文芸関連プログラムを対象とした研究が、音楽分野で朝鮮音楽を中心とした音楽関連プログラムの研究が行われており、特に二重放送期以降に焦点が絞られている。
そこでこの発表では、娯楽プログラムの中で最も高い比重を占めていた音楽プログラムに焦点を絞り、ラジオが音楽を伝える媒体として形成される過程でどのような特徴を示してきたのかについて、主に1920年代の『京城日報』に掲載されているJODKラジオプログラムを網羅的に検討することによりその実態を明らかにする。
□ シンポジウム「近現代韓国・朝鮮における街頭集会・示威」
月脚達彦「趣旨説明:近現代韓国・朝鮮における街頭集会・示威を見る視点」
三・一運動は「万歳事件」とも呼ばれたように、ソウル鍾路のパゴダ公園(塔洞:タプコル公園)に集まった人々が、学生の「独立宣言書」朗読ののち、「万歳」を唱えて街頭を示威行進したことに端を発する。大韓帝国の国旗だった太極旗も登場した。同日、「万歳」示威行進は平壌・宣川・義州など、北部の都市でも行われている。それは地方にも拡散し、やがて暴力行使も伴うようにもなっていった。朝鮮全土での運動への参加者は100万人以上とも推測され、大規模な独立運動を予想していなかった朝鮮総督府は、それまでのいわゆる「武断統治」から、斎藤実総督の標榜する「文化政治」へと統治の方針を転換することとなった。日本の支配からの独立は実現しなかったが、1920年代の朝鮮では都市部を中心に近代が浸透し、社会の変容が本格化することになった。
このように、三・一運動は近代朝鮮のターニング・ポイントの一つとなっているのだが、解放後の韓国においても、街頭での集会・示威が特に政治の面で時代の画期をもたらした例は数多く存在する。1960年の「四月革命」、1987年の「6月民主化抗争」などが代表的なものであり、2016年の「ろうそく集会・示威」が記憶に新しいところである。三・一運動から100年を迎えた2019年の本研究会大会シンポジウムは、街頭で行なわれる集会と示威をテーマにして、歴史学、社会学、文化人類学等の分野からの報告を受け、去る100年余りの韓国・朝鮮社会の変化について議論することとしたい。
ソウルにおける万歳と太極旗による街頭集会と示威の起源は、1896年に結成された独立協会の運動に遡る。独立協会は日清戦争を機とした清との宗属関係の廃棄を受けて、1895年に撤去された迎恩門の跡に独立門を建設することを目的に結成された。1896年11月21日の「独立門定礎式」では、『独立新聞』の報道によると、太極旗を飾った仮設の門のもとに「五・六千人」の内外国人の来賓が集まり、見物人が「人山人海」を成すなか来賓の演説、学校生徒の愛国唱歌斉唱と「大君主陛下万歳」などが行われたという。その後、独立協会は国家の慶祝日などに際して、独立館で慶祝会を挙行する。
もっとも独立門と独立館は西大門外に位置し、ソウルの城内ではない。独立協会がロシアの利権要求とそれを招来した政府を批判する「万民共同会」を鍾路で開催したのが、1898年3月10日である。『独立新聞』の報道によれば、米廛の市丁が会長に選出され、演士が白木廛の楼上で演説したという。同12日には独立協会の主催ではない万民共同会が鍾路白木廛で開催され、このときは会を妨害しようとした人物と演士・聴衆との間で投石の事態が繰り広げられたという。
鍾路で万民共同会が開催されるようになった1898年には、開国紀元節・万寿聖節などの慶祝会が独立門前で行われたのち、独立協会会員が太極旗を掲げて行進し、鍾路を経て仁化門(慶運宮南門)前で「皇上陛下万歳」を唱えるようになった。11月、政府による幹部の逮捕と「協会禁止」の勅令によって独立協会は解散させられるが、万民共同会が褓負商団体との流血戦も伴う示威を続けた結果、高宗は仁化門に臨御して独立協会の再開を許す親諭を下した。しかし独立協会急進派の運動は激化を続け、万民共同会は同年末に解散させられ、次いで独立協会も解散させられた。
独立協会および万民共同会に関する歴史学の研究では、かねてからその民族主義・民主主義的性格をめぐって議論がなされてきた。しかし、ここでは1898年の鍾路や慶運宮門前で行われた慶祝行事や集会・示威に注目したい。日清戦争後、朝鮮では「独立」の機運が高まった。もはや中国の「属邦」ではなくなった以上、朝鮮の君主は諸外国の君主と同格になり、朝鮮人民も「忠君愛国」の精神を涵養してそれに相応しい地位を得なければならないというのが独立協会の主張である。
そうして独立門が建設され、慶祝の場には演説、愛国唱歌、国旗、万歳などが登場する。鍾路の空間的位相は、漢城判尹李采淵と総税務司マクレビー・ブラウンによる道路整備、1897年の高宗の皇帝即位などを経て、皇帝が宗廟・清涼里洪陵(明成皇后陵)へと行幸する「御路」に変貌していった。また、高宗がロシア公使館から還御した慶運宮(徳寿宮)の仁化門・大安門(大漢門)前も慶祝の場となるとともに集会・示威が行われる広場となっていく。 第一次世界大戦の終結と民族自決の気運の高まりという世界史的状況のなかで起こった三・一運動は、もう一方で高宗の因山(3月3日)を翌々日に控えたソウル鍾路に位置するパゴダ公園(1902年に大韓帝国の軍楽隊の演奏場として完工したものと推測される)を発生地とし、万歳を唱える行進は徳寿宮大漢門前や昌徳宮敦化門前へと向かっていった。それが朝鮮全土を覆う示威へと拡大していったのである。
このように、三・一運動における人々の行動の在り方は、日清戦争後の近代移行期の朝鮮社会に現れた様々なシンボル、身体所作、空間的位相、慶祝や因山などの儀礼などが絡まり合ったものだったと言えよう。解放直後には左右の政治勢力による紀念集会において、三・一運動の記憶が喚起されることにもなる。南北分断後、三・一運動、特に「民族代表33人」が署名した独立宣言書をめぐって、南と北の歴史学会では評価が対立するようになるが、コメモレーションという点も三・一運動は、韓国・朝鮮の現代史に関する重要なテーマとなりうる。 以上、近代史研究の立場から、独立協会・万民共同会、三・一運動の街頭集会・示威について概観した。広い意味での「政治文化」の視点からの整理で、場所はソウルに限られているが、社会学、文化人類学等の各分野における集会・示威に関する研究状況を踏まえれば、また異なる視点から近現代の韓国・朝鮮の社会と文化について議論することが可能だろうと思われる。
趣旨説明に続いて、特に19世紀末から三・一運動へと至る時期の街頭集会や示威に関する事例の分析とともに、近現代韓国・朝鮮における街頭集会・示威を考察する視点について、近現代日本の事例などを踏まえて議論の材料を提示したいと思う。
松谷基和「三一運動における万歳の意義――近代的ネイションとしての『朝鮮』の産声」
かつて牧原憲夫が発表した論考「万歳の誕生」は、「万歳」という儀礼の誕生が、近代日本の国民意識の創出に果たした役割を明らかにした興味深い論考である。牧原は明治憲法記念祭で初めて誕生した「万歳」という儀礼が、民衆が直接に天皇に発声することを許した点で画期的であり、民衆が頻繁に「万歳」と唱える機会を持つことで、この儀礼が唱える側と受ける側の間に存在する現実上の身分や権利の差異を一時的に忘却させ、天皇を中心とした国家共同体への共属意識を民衆に植え付ける――つまりナショナリズムを創出する――上で、非常に効果的であったことを明らかにした。
しかし、この論考を前提とするならば、1919年に日本の植民地朝鮮で発生した大規模な抗日民族運動、すなわち「3・1独立運動」においても「万歳/マンセイ」が唱えられたことをどのように説明し、理解すべきであろうか?日本において天皇を中心とした国民としての共属意識の創出に一役買ったとされる「万歳」が、朝鮮では全く逆に日本への抵抗運動の手段として使用されたとすれば、実に不思議なことである。
本稿はこの問いに答えるべく、日本と朝鮮において「万歳」が集団儀礼として定着していく歴史過程を明らかにする。結論から述べれば、君主を礼賛する語彙としての「万歳」は朝鮮にも存在したが、それは中華王朝の皇帝にのみ使用され、朝鮮国王には「千歳」が使用されていた。また、こうした語彙の使い分けは、華夷秩序における権力ヒエラルキーを可視化する記号にすぎず、民衆間の共属意識を創出する儀礼としての「万歳」は存在しなかった。しかし、日清戦争で華夷秩序が崩れ、大韓帝国が成立すると、大韓皇帝にも「万歳」が使用されるようになる。ただし、朝鮮ではあくまでも「万歳」を唱える対象は皇帝に限定され、唱える側と唱えられる側の対象を限定しない日本型の「万歳」儀礼は普及しなかった。
ところが、日本が朝鮮を保護国化し、やがて併合に至る過程の中で、日本の学校教育や公的な行事の場を通じて日本型の「万歳」儀礼が朝鮮社会にも移植され、朝鮮の民衆の間でも日本の天皇をはじめとして、大韓皇帝以外の一般人にも「万歳」を唱える文化が浸透していった。こうした背景があって、3・1独立運動時にも、朝鮮の民衆は皇帝個人ではなく、「大韓/朝鮮」という想像の共同体に対して「万歳」を唱えることができたのである。
このことは、朝鮮の民衆が日本から輸入された「万歳」儀礼を、逆に日本に対抗する朝鮮ナショナリズムの創出の手段として有効に使用したと評価もできる。しかし、その背景には、日本の植民地権力が朝鮮王朝の権威を失墜させ、皇帝への垂直的な忠誠心を表す語彙としての「万歳」を自由化し、君民間の一体性や民衆間の水平的な共属意識を創出する儀礼としての「万歳」を普及させていた事実があり、大韓皇帝の権威が無化されなければ、朝鮮では民衆が自らの選択する共同体や国家に対して「万歳」を唱えることはできなかったと考えられる。こうした観点から評するならば、3・1独立運動で唱えられた「万歳」は、朝鮮王朝の完全なる終焉を告げる晩鐘であると同時に、新しい近代的ネイションとしての「大韓/朝鮮」の誕生を告げる産声であったともいえよう。
真鍋祐子「三・一運動からキャンドル集会まで ―─死生観と歴史認識から考える」
2015年11月14日、ソウル光化門広場で開かれた第一回民衆総決起集会で、全羅南道宝城郡から参加していた白南基農民(68歳)が、機動隊から放水銃の集中砲火を浴びて意識不明の重体に陥った。意識が戻らないまま約10か月後に白が死去すると、2016年11月12日の第二回民衆総決起大会にあわせて葬儀が決行され、光化門をめざす霊柩行列が警察と対峙した。この時、白の出身地である全羅道の各地から、農民たちが東学農民抗争の進軍になぞらえ、光化門をめざして「全琫準闘争団」と呼ぶトラクター部隊を北上させたが、高速道路を出たところで警察の封鎖にあい、引き返さざるをえなかった。
このエピソードは、2016年のキャンドル集会をそこから120年余りも遡った東学農民抗争に接続させることで、運動の意味を民族史の中に文脈化させる歴史意識の一面を示している。また、この時点で光化門一帯はすでに、2014年4月16日に起きたセウォル号惨事の遺族たちが真相究明を求めて籠城する追悼空間として存在しており、民衆総決起大会はそこに接続される形で行われたといえよう。2015年4月19日に行なわれた「セウォル号1周忌追慕礼拝」で、韓完相は東学農民抗争から三・一運動にかけての「抵抗の歴史」を振り返り、「過ぐる120年間の民族と民衆の苦しみが、解放後、セウォル号の姿に集約的に表されている」と語っている。このように三・一運動は東学農民抗争とともに、民族史を貫くとされる「抵抗の歴史」の起点に位置づけられている。
本報告では三・一運動に焦点をあてつつ、そこからキャンドル集会へと連繋される歴史意識と、人々を運動へと突き動かす「歴史的想像力」がどのようなものかを考える。これは三・一運動を源泉とした大韓民国臨時政府の位置づけをめぐるニューライト勢力との「記憶の抗争」の一端でもあり、その中で運動主体が三・一運動をどのように捉え、表象しているかを見ていく。また、平和の踏み石(평화 디딤돌、韓国)、東アジア市民ネットワーク(日本)、東アジア共同ワークショップ実行委員会(台湾)の共催で、今年8月にソウルで開催された東アジア共同ワークショップ「3・1からろうそくの火まで―東アジアの平和のための一歩」の取り組みを例に、三・一運動からキャンドル集会へと連繋される歴史意識が、プログラムのひとつ「3・1からろうそくの火までのフィールドワーク」にどのように反映されているかを検討する。
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内