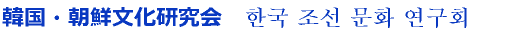![]()
2021年度の研究大会は、10月24日に佛教大学二条キャンパスで開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の状況により、オンラインで開催することといたしました。
韓国・朝鮮文化研究会
会長 月脚 達彦
会長 月脚 達彦
第21回研究大会委員会
委員長 鈴木 文子
委員長 鈴木 文子
□ 日時:2020年10月24日(土) 10:00~17:40
□ 場所:Zoomオンライン・ミーティング
□ 後援:佛教大学
□ プログラム
| 9:50 | Zoomミーティングへの入室開始
|
|
| 10:00~12:00 | 一般研究発表(発表30分,質疑応答10分) 司会:秀村研二・澤野美智子 鄭孝俊「KPOPファンダムにおける聖地創造と「非場所」の変容実践:ソウル地下鉄駅構内に掲出されるアイドル応援広告を事例に」 安昭炫「現代韓国社会における学徒兵記念の大衆化」 森田和樹「朝鮮戦争期の韓国における徴兵忌避と脱走兵」 |
|
| 12:00~13:00 | 昼休み |
|
| 13:00~17:40 | シンポジウム「朝鮮戦争と向き合う──分断状況の思想・文化・個人」 司会:板垣竜太・辻大和 鈴木文子「趣旨説明」 鄭祐宗「戦後日本の国際法学者における朝鮮問題認識」 松岡とも子「朝鮮戦争期臨時首都釜山における美術活動――金煥基(1913-1974)ほかソウル避難画家を中心に」 宋基燦「韓国軍出身の朝鮮学校研究者:朝鮮学校の現場で自分の中の身体化した分断の記憶と向き合うと言うこと」 コメント:鄭炳浩 総合討論 ※なお、例年研究大会の際に開催している会員総会は、オンライン開催の都合上、今回に限り電子メールでの審議にかえさせていただきたく存じます。詳細につきましては改めてご連絡いたします。なにとぞご了解のほど、よろしくお願いいたします。 |
□ 問い合わせ先:21taikai★askcs.jp(←★を半角のアットマークに変えて下さい)
(1) 一般研究発表
鄭孝俊「KPOPファンダムにおける聖地創造と「非場所」の変容実践:ソウル地下鉄駅構内に掲出されるアイドル応援広告を事例に」
本発表は、韓国ポピュラー文化と日本のファンの相互越境が韓国においてどのようなファン実践を生産消費し、またそのことによって韓国のツーリズム空間がどのように変容しているのかについて探究するものである。とくに近年、世界を席巻しているBTS、BLACKPINK、TWICEなどのK-POPアイドルに着目し、対するファンの感情的没入が韓国において聖地“創造”と呼べるような空間生産を構成し、また、それ自体を観光主体であるファンが消費するという形の聖地巡礼ツーリズムが実践されていることを明らかにする。従来の聖地巡礼ツーリズム研究は、寺院仏閣や神話性を付与された自然景観、さらには映画やドラマ、アニメに登場する実際の場所をファンが訪れる観光実践に関する研究が多い。これらの議論に登場する聖地の生産者と消費者の関係が対立的であるのに対し、ソウルの地下鉄駅構内に出現するK-POPアイドルの応援広告は、ファンがSNSで募金を集めて設置することでアイドルの誕生日やデビュー記念日を儀礼的に祝い、ファン自身が応援広告を訪れて記念写真を撮影するほか、ファンが付箋にアイドルへのメッセージを書いて広告に張り付け感情的没入を経験するなど、聖地の生産と消費が同一のファンコミュニティによって行われている点に特徴がある。それらのメッセージにはアイドルへの温かい応援、真剣な祈りやいたわりがあふれた極めて真摯で敬虔な態度が現れており、ファン聖地巡礼の核心を成している。
地下鉄広告にはワイドカラー照明広告、スクリーンドア広告、デジタルポスター広告、ポスター広告などがある。ソウル交通公社によると、アイドル応援広告は2014年には76件にすぎなかったが、16年から急増し18年には2,000件を突破。19年は2,166件に上り、そのうちBTSの広告が227件で最も多かった。このようなアイドル応援広告の急増はソウルの都市空間にも変容をもたらしており、ソウルの都市デザインにファンが主体的に関与していることを物語っている。人類学者、マルク・オジェによれば、空間における循環の整った地下鉄駅構内のような場所は「非―場所」と定義され、通行人には通過という匿名性の強い行為が平均的に求められる。これに対し、地下鉄駅構内に掲出された応援広告には、アイドルとファンの実名的な関係性が明示されている。ファンは主体的に自身の身体を地下鉄駅構内に埋め込み物語を作り出すことで、アイドル応援広告を「場所」として生産・消費し、通過が本来の目的である地下鉄駅構内という空間を変容させる観光実践を行っていると言えるのではないか。
本発表のために筆者は2019年10月13日から15日までソウル地下鉄サムソン(三成)駅(ソウル特別市江南区)の構内に掲出されたアイドル応援広告、並びにファンが広告に張り付けた付箋に書かれたメッセージの内容を調査するとともに、アイドル応援広告を実際に見に来たファンへのインタビューを実施した。これらのデータを分類、分析することで、K-POPファンによる聖地巡礼実践とソウルの都市空間変容の関係性をオジェの「非-場所」の概念を参照しながら論じていきたい。
安昭炫「現代韓国社会における学徒兵記念の大衆化」
朝鮮戦争勃発60周年を契機に、韓国社会では大衆的な媒体を通した学徒兵記念が開始された。2010年に公開された『戦火の中へ』と2019年に公開された『長沙里:忘れられた英雄たち』は、朝鮮戦争期学徒兵が参戦した浦項女子中学戦闘と長沙上陸作戦をそれぞれモチーフにしたブロックバスター戦争映画である。両作品はそれぞれK-POPアイドルを主人公に起用しており、商業面での成功と学徒兵の認知度向上を試みた。
朝鮮戦争に参戦した学徒兵とは、中学生から大学生までの学生によって構成された義勇兵のことである。約27万人がこの学徒兵として参戦し、そのうち約2万余人が戦闘に参加したという。しかしその規模に比べて、学徒兵は1990年代に至るまであまり注目されてこなかった。1959年の兵役法改正において朝鮮戦争当時参戦した学徒兵に対する兵役免除がなされたが、世論はそれを当時蔓延した学生の兵役忌避の観点から批判した。1960年代以後、学徒兵参戦者団体は右翼団体となり政治活動に加担した。1980年代には政府の施策により参戦者団体がすべて統合された。1990年代初め、統合政策が廃止されてからは地域ごとの学徒兵団体が多く設立され、記念と追悼活動が活発に行われるようになった。このような記念・追悼活動が、朝鮮戦争勃発60周年の2010年を前後して、国家によって積極的に管理され始めた。戦争記念館における展示コーナーの新設、地方記念館のリモデリング開館、地方教育庁による書籍刊行、国防部軍史編纂研究所による研究書の公刊がこの時期同時進行で行われた。そしてこれらの展示や資料は、祖国を守るために「ペンの代わりに銃を握った」学徒兵の愛国心と勇気を称えている。すなわち、「軍事化された青少年」のイメージが、愛国の衣をまとわされて生産されるようになったのである。
本報告は韓国の学徒兵記念の様相を、少年兵問題とグローバル社会における南北問題の脈絡から捉える。欧米諸国には、第1次世界大戦期に少年兵を戦闘に用いた歴史がある。このような少年兵は戦争英雄として記憶されている。そして現代では、大学進学前の学生を対象とした特別な経験として、兵営体験プログラムが宣伝されている。このような「軍事化」では、教育を十分に受けたがゆえに自発的に戦闘に参加する冒険志向の白人の少年のイメージが表象される。その反面、先進国と国際機構、NGOが主導する、子ども兵の使用に反対するキャンペーンでは、中東・アフリカの子ども兵のイメージが、純粋性と機会と権利を奪われ放置された少年期を送る有色人種の少年に代表させられる。いずれにおいても軍事化される少年が表象されているが、まとわされるイメージは正反対のものである。このように近年の少年兵問題研究は、グローバルノースのナラティブに内包された帝国主義と人種主義の視線を指摘し、グローバルノースにおける少年兵記念の方式を考察している。
本報告は、今日の韓国における学徒兵記念の動きもグローバルノースの文脈から大きく離れないと診断し、学徒兵の経験の映画化とその映画をめぐる学徒兵記念のナラティブを分析し、今日の韓国の急速な発展に伴うグローバルノースの一員としての位置づけが学徒兵の記念に表れていることを明らかにする。
【参考資料】
国防部軍史編纂研究所『6・25戦争 学徒義勇軍研究』(ソウル:国防部軍史編纂研究所)2012年。 Lee-Koo, K “Horror and Hope: (re)presenting militarised children in global North-South relations”, Third World Quarterly, 32(4), 2011, pp.725-742.
森田和樹「朝鮮戦争期の韓国における徴兵忌避と脱走兵」
近年、朝鮮戦争に関する研究分野では、兵士たちの戦場体験に関する研究や村落レベルでの社会的な葛藤の構造を解明した研究、あるいは人びとの広範囲に及ぶ移動状況を描きだした研究など、朝鮮戦争期の社会の実相を「下からの」視点から描きだした研究が多数発表されてきた。だが、いまだ十分に歴史化・記憶化されていない現象がある。それは1950年代の韓国社会において徴兵忌避および軍隊からの脱走が頻繁に起こっていたという現象である。実際、記録されている範囲でいえば、朝鮮戦争期の韓国では、最も多い年で徴兵忌避者が29万人以上、脱走兵が2万5,000人以上出ていた。
本発表の目的は、朝鮮戦争期の韓国における徴兵忌避と脱走兵の実態を解明することにある。ここでは新聞や裁判資料、手記などに依拠し、つぎの3つの観点から徴兵忌避と脱走兵について分析する。
第一に、流動性である。朝鮮戦争の特徴のひとつは、とりわけ戦争の初期段階において戦況が幾度も逆転した点にある。こうした戦況の変化は、個々の兵士からすれば、軍隊からの脱走の余地が広がる機会になっていた。一方、自らの居住地が戦場と化すなか、多くの人びとが戦火を避けるために移動していた。その結果、政府は徴兵対象者の情報を把握できないでいたのである。つまり、戦況の流動性が前線に動員された兵士たちの脱走の可能性を広げていたとすれば、避難による人びとの移動という意味での流動性の高まりは軍による徴兵から逃れる余地を広げるものだったのだ。
第二に、徴兵制と家族の関係性である。多くの場合、徴兵忌避や軍隊からの脱走という行為は、どれほど忌避行為への諸個人の意志が強かったとしても、その行為主体を匿う社会的な空間や関係性がなければ失敗に終わってしまうだろう。朝鮮戦争期の脱走兵や徴兵忌避者の事例を検討すると、家族が軍隊からの忌避者を匿うという重要な役割を果たしていたケースが多数発見できる。つまり、ここに国家による徴兵機能と家族という集団の間に、事実上の対立が生じていたことを見て取ることができる
第三に、「国境を越える逃走圏」である。個々の脱走兵や徴兵忌避者の逃走範囲を検討すると、彼らの移動範囲は朝鮮北部から日本にまで及んでいたことがわかる。つまり、徴兵忌避者や脱走兵のうち一部は、韓国政府の実質的な支配地域から逃れるために、積極的に朝鮮民主主義人民共和国の側へ「越北」したり、「密航」という手段を通して日本の朝鮮人集住地域に身を潜めたりしたのである。こうした点を踏まえれば、かつて梶村秀樹が「国境をまたぐ生活圏」として概念化した朝鮮人独自の生活領域が、軍隊ないしは戦争状況からの逃避という文脈において「国境を越える逃走圏」の役割を担っていたといえる。
(2) シンポジウム「朝鮮戦争と向き合う──分断状況の思想・文化・個人」
鈴木文子「趣旨説明」
1950年6月25日の朝鮮戦争勃発より70年の時を経た。本シンポジウムは、朝鮮戦争および、その後の南北の分断状況が、朝鮮半島と日本に住む人々の思想、文化、意識にどのような影響をもたらしてきたか。それらが、これまでの韓国朝鮮研究にどのような影響を与え、あるいは与えなかったのか。そこからどのような今後の研究の視座を考えることが可能か。このような問いに関して、多分野の研究者が集まり共に考えることを目的とする。
植民地時代と現代の連続性を意識する研究は、この四半世紀ほどの間に多くの成果を示してきた。しかし、朝鮮半島のみならず東アジアに大きな影響を及ぼした朝鮮戦争のインパクトについての考察を抜きに、連続や断絶は論じることができないはずである。にもかかわらず、朝鮮戦争がそれ以降の社会・文化にどのような影響を及ぼしたかに関する研究は、いまだ研究の途上にあるといわざるをえない。
一方、2000年代に入り、朝鮮戦争をめぐる研究にも新しい潮流があらわれてきた。それは、戦争勃発の起源や主体に関心を置いた初期の政治外交史から、思想史、地方史、社会史、文化史へと、また、歴史学のみならず、社会学、文化人類学に至るまで、多様な分野で展開されるものとなった。その対象も、政府や軍のレベルのみならず、民衆、村落、個人にまで広がり、それにともない、口述史や地域資料などミクロな視点や資史料も用いられるようになっている。その中で、戦乱による都市や村落地域の破壊、南北分断の固定化、それに伴う人々の移動・交錯、あるいは社会的葛藤や心の傷などを要因とした、解放後から朝鮮戦争前後の状況に関する記憶・記録の分断・忘却・欠如といった問題が浮上する。それらの回復は、現代の植民地認識や南北朝鮮に対するイメージ、韓国社会内の分断意識や日本におけるその理解やラベリングなど、朝鮮半島の社会文化とその表象性を考察する上で重要となる。すなわち、このような失われた記憶・記録を追い求めつつ、現代をポスト朝鮮戦争状況として再認識することは、韓国朝鮮研究のみならず、日本における朝鮮半島認識を考える上でも必須の作業といえるであろう。
本シンポジウムでは、上記のような問題意識と研究状況を踏まえ、3人の発表者に登壇していただく。日本人の国際法学者の朝鮮戦争に関する法理を分析し、分断状況における国家と政府、戦争と内戦に関する認識の系譜を検討する鄭祐宗氏、画家たちにとっての臨時首都釜山への疎開の経験とその影響を美術史の観点から論じる松岡とも子氏、兵役体験から朝鮮学校研究に至るまでの自らの経験を踏まえ、ポスト朝鮮戦争の現代を考える宋基燦氏らが問題提起を行う。
鄭祐宗「戦後日本の国際法学者における朝鮮問題認識」
戦後日本の国際法学者は朝鮮問題をめぐっていかなる前提に立ち、いかなる角度から議論し、学術的あるいは実践的にいかなる問いにチャレンジしたのか。この主題について条約解釈を基軸とした「実定法主義の角度」と、さらには現代国際法という営為そのものの構造把握を基軸とした「実定法主義を超えた角度」の二段の構えから迫ろうとするのが本報告である。
まず第一の構えとして、横田喜三郎(1896-1993)と入江啓四郎(1903-1978)という1950年代初頭における二人の国際法学者の相異なる朝鮮問題認識のあり方から接近したい。ここで横田と入江を同時に取り上げる理由は、両者の認識上の重要な分岐を明らかにするのみならず、実体法主義という共通土俵を掴もうとするためである。1950年当時東京大学で国際法を教えた横田は、1950年6月25日直後から朝鮮での戦闘を「内乱ではなく戦争」とする論陣をはり、同年11月に『朝鮮問題と日本の将来』(勁草書房、1950年)を刊行した。横田は、朝鮮分断状況の二国二政府論、北緯38度線の国境線論、朝鮮動乱の国家間戦争論を展開したが、国連諸決議を軸とした国際法優位一元論のもとに朝鮮国内法の視点を全的に考慮に入れない方法的視座に立った。他面また法=強制説に立ち国連諸決議による韓国援助を将来的な日本に対する国連集団安全保障の前例と見なしたが、国連諸決議の強制力についての分析の緻密さに欠けるものであった。他方当時時事通信社時事研究所長であった入江は横田と前提を異にし、朝鮮分断状況の一国二政府論、北緯38度線の非国境線論、朝鮮動乱の内乱論を論じ、「国連軍」派兵を干渉の文脈で捉えた。入江は数多くの評論を手掛けたが、一貫して朝鮮動乱を「戦争ではなく内乱」とする解釈をとり、国連文書に対する戦後処理協定優位の国際法解釈と、朝鮮国内法の視点から議論を立てた。横田と入江の認識上の分岐は、一見すると国連中心と戦後処理協定中心の間にあるように見えるが、見逃せない点は朝鮮の主権尊重義務の如何にこそある。
本報告の第二の構えとして、1960年代に日韓問題を論じた祖川武夫(1911-1996)、石本泰雄(1924-2015)に焦点を当てる。祖川と石本が、「実定法主義」を乗り越えるべく目指した構えは現代国際法という営為そのものの構造把握であり、とりわけ石本のそれは戦争違法化が国際法構造の枝葉的変化ではなく、規範構造そのものの転換であることを説く点で反植民地主義の実践的国際法研究に通じた。古典的国際法に人民が合わせるのではなく、人民に現代国際法が合わせるという発想の転換が朝鮮問題認識をいかに刷新したのかという点が検討される。
松岡とも子「朝鮮戦争期臨時首都釜山における美術活動――金煥基(1913-1974)ほかソウル避難画家を中心に」
朝鮮戦争期、臨時首都となった釜山には、国の行政機関や大学、博物館などの教育文化施設、企業などとともに全土から多くの避難民が押し寄せた。本発表では、当時の韓国画壇を担っていたソウルからの避難画家を中心に、朝鮮戦争期の臨時首都釜山における制作活動に焦点を当てる。
解放後の朝鮮において画壇の中心的存在となったのは、日本に美術留学した植民地期世代の画家たちであった。解放直後、米ソの信託統治から1948年の韓国政府の樹立へと反共姿勢がいっそう強められていく。一部の画家たちは新設されたソウル大学美術学部などの植民地期に得られなかった国内の美術専門教育の場で教鞭を取り、50年美術協会といった左右派の合同団体の創設を試みるなど、対立構造の中にありながらも朝鮮の知識人として新たな出発を模索した。しかし結局は様々な喪失感を抱え釜山へ避難する。
本発表では始めに、臨時首都釜山における特有の美術活動について、従軍画家団の活動や大韓陶器における輸出陶磁の絵付け作業、移転した国立博物館や茶房での展示活動、李舜臣銅像制作などの例を先行研究から整理する。加えて、ソウルから避難した画家金煥基(1913-1974)や白榮洙(1922-2018)、彼らを迎えた釜山在住の李俊(1919-)らを中心に、当時の随筆や近年の口述筆記記録から朝鮮戦争期の作品を振り返る。
画材の不足はもとより、展示場所も作品の購入者も得難い避難地において、画家たちは形ばかりの従軍画家団の身分証によって配給を受けるか、看板製作や雑誌の挿画を描くなどしてわずかな生活費を得ていた。現存作品もペン画や水彩画が多く、画布の作品においても制作背景が特定できるものは非常に少ない。しかしながら、プロパガンダ的な広告や戦時下の姿を写す作品を除き、当時の団体展への出品作品の記録や雑誌の挿画において多くみられるのは植民地期以降いつの時期にも描かれて来たような、韓服の女性像や韓屋、梅花や陶磁器といったいわゆる朝鮮の文化を象徴するモチーフである。
こうしたモチーフについて、本発表では画家の当時の生活や分野を越えた人間関係、作品の発表媒体等から作品分析を試みる。このことにより、朝鮮の文化を象徴するモチーフの作品の背景に見られる、植民地留学世代の画家の解放前後からの問題意識や韓国政府が急速に進める国民国家体制、そして米軍や国連軍の駐留による文化支援といった様々な影響関係が混在した臨時首都釜山における美術活動を改めて考察する。
宋基燦「韓国軍出身の朝鮮学校研究者:朝鮮学校の現場で自分の中の身体化した分断の記憶と向き合うと言うこと」
人類学の調査方法論では、研究の段階において研究現場から「離れる」ことが重要である。しかし、ある意味人類学者は、自分の「現場」から離れることはできないのである。「現場」に参与する過程で、そして「現場」で研究を進める過程において、人類学的実践は人類学者自身のアイデンティティを変化させ、生き方に関わるからだ。
朝鮮学校に関する民族誌を発表した後、私は朝鮮学校に自分の子供たちを送る「保護者」となった。現在中級学校(中学校)1年に息子が、初級学校(小学校)4年に娘が通っている。かつては自分の現場研究の対象であった朝鮮学校とその学生と保護者・先生たちは、韓国出身の私が朝鮮学校に自分の子供を通わせている事実に驚きながらも、もはや同じ立場になったと喜んでくれた。しかし朝鮮学校に通う私の子どもたちが日常的に話している「ウリナラ(我が国)」が、父親である私が生まれ育ったところと異なる場所を意味しているという事実は、少し自分自身を戸惑わせる時がある。もちろん朝鮮学校の現場を研究してきた私がこのことを予想しなかったわけではないが、朝鮮学校の日常で出くわす「北朝鮮」の存在は、自分の中で長年身体化している「韓国人」の記憶を想起させるのである。
1970年に生まれた「韓国人」として私は、子供の頃から「反共教育」を受けながら成長した。その教育の中で、いつも北朝鮮は間違った「悪」であり、怖い存在であった。高校からは軍事教練を受けながら、北朝鮮という悪は、自分の力でいつか倒さないといけない「敵」と変わっていく。そのような「敵」としての北朝鮮のイメージは、軍隊の経験を通して完全に身体化されることになる。軍隊では北朝鮮の敵と戦う具体的な戦術を学び、日々その練習を行うからだ。そのような経験の中で、私は北朝鮮に対して「同胞」というイメージをあまり持たなくなっていた。自分が大学生の時に、韓国大学生の中には北朝鮮に親しみを持っている「N L派」の学生たちも少なくなかったが、私を含めて多くの大学生は、北朝鮮に対して否定的なイメージを持っていた。
このような個人的背景を持っている私が、初めて朝鮮学校を訪問した時は、容易い決定ではなかったが、私が朝鮮学校に自分の子供たちを通わせると決めた理由は次の通りである。まず、以前の人類学的研究を通して私は朝鮮学校が「良い学校」であるという確信があったからである。選択できるのなら自分の子供を「良い学校」に通わせたいというのは全ての父母たちの共通した欲望であろう。ところが、この「良い」という基準には個人差があり、それは父母自身の教育観と密接な関連があるだろう。私の場合、共同体が生きている学校である点と、日常的に多様な境界を体験しながら成長できる教育現場である点から朝鮮学校を「良い学校」と判断した。
朝鮮学校の父兄になったもう一つの理由は、父兄の立場として、朝鮮学校の現場調査を継続することができることを期待したからでもあった。しかし、親として自分の子供が含まれている現場を観察するということは、新しい困難が伴うということをまだ知らなかった。運動会や学芸会時は、他の保護者たちにまぎれて、ビデオカメラで映像を記録し観察する方法は変わらないが、以前のように、全体的な状況を記録して理解しようとする映像ではなく、いつしか自分の子供を中心に記録をしている自分を発見する。しかし、学生と保護者、教師の生活環境と詳細なライフヒストリー、学生が学校と家庭の間で見せる変容、特に学校で学ぶ内容を学生の親の立場から理解することができることなど、朝鮮学校の父兄になる前には、アクセスしにくかった部分が表示されるようになった。このように、朝鮮学校コミュニティにおける外形的なメンバーシップは確保することができたが、上記のように「韓国人」が朝鮮学校の中で持つ特殊な立場は、まだ変わらず研究を容易にする部分もありながら、同時に関係の形成を制限する限界として作用しているようだ。さらに、「韓国人、朝鮮学校の研究者」という現場の認識は現場での多くの出会いや活動に1つの方向性を提示する場合が多く、自然な現場調査を制約する部分もある。今回の報告ではその中で、私の中の「韓国軍」の記憶が朝鮮学校の研究に及ぼした影響について考察する。
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内