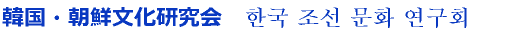![]()
開催方式につきましては,昨今の情勢を踏まえ,対面とオンラインの併用とすることとしました。対面参加の場合には,手指の消毒と会場でのマスク着用等,感染予防対策の徹底をよろしくお願いします。参加費は無料とします。対面参加もオンライン参加も,いずれも事前申込みが必要です。参加を希望する会員諸氏は,下記の要領に従ってお申し込みください。
韓国・朝鮮文化研究会
□ 日時:2022年10月22日(土) 10:00~17:30第23回研究大会委員会
本田 洋
本田 洋
□ 開催方式:対面とオンラインの併用
□ プログラム
| 9:40 | 対面受付・オンライン入室開始
|
|
| 10:00~12:00 | 一般研究発表(発表30分,質疑応答10分) 司会:水谷清佳・仲川裕里 重岡こなつ「村落祭祀の伝承主体としての「保存会」─K城隍祭硏究保存会の事例から」 辻大和「朝鮮王朝期日常生活での薬用植物の消費について」 柳川陽介「朝鮮日報社の出版事業と文学史 1930 年代を中心として」 |
|
| 12:00~12:50 | 昼休み |
|
| 12:50~13:20 | 会員総会 |
|
| 13:30~17:30 | シンポジウム「「巫俗(シャーマニズム)」「迷信」再考」 司会:川瀬貴也・辻大和 川瀬貴也「趣旨説明」 古田富建「巫俗的韓国キリスト」の再考 新里喜宣「巫俗は「宗教」か、「宗教ではない宗教」か―祈福信仰、宗教概念、普遍的価値観という桎梏―」 影本剛「迷信、あるいは生の原動力 ――近代朝鮮文学とジェンダーの問い」 コメント:川上新二 総合討論 |
□ 当日資料:発表・報告・総会の資料は電子媒体のみで配付します。対面参加の方にも印刷配付しませんので,事前に印刷してくるなど,それぞれ準備をお願いします。
□ 参加費:対面・オンライン参加ともに無料とします。
□ 問い合わせ先:23taikai★askcs.jp(←★を半角のアットマークに変えて下さい)
□ 発表・報告要旨
(1) 一般研究発表
重岡こなつ「村落祭祀の伝承主体としての「保存会」─K城隍祭硏究保存会の事例から」
本発表の目的は,村落祭祀の伝承主体としての「保存会」に注目し,文化財政策という支配的な文脈を受容・内面化しながら紡ぎ出される個々の実践に対する考察をおこなうことである。事例としては,京畿道始興市でおこなわれるK城隍祭とその保存会(K城隍祭硏究保存会,以下「研究保存会」)を扱う。
K城隍祭は京畿道始興市と京畿道安山市の境界に位置するK山頂で毎年陰暦10月3日におこなわれるマウルクッ(村祭)である。祀られる城隍神が金傅大王(新羅最後の王である敬順王)であることから高麗時代にはすでに始まっていたものと推測されるが定かでない。「始興K城隍祭」は1993年京畿道民俗芸術大会に初出場し発掘賞を受賞したのち,2015年に京畿道無形文化財第59号に指定されており,本発表で取り扱う「K城隍祭硏究保存会」は民俗芸術大会出場に際して1993年に結成された。
韓国の場合,無形文化財は農村の年中行事とは結びついても,これを支える地域社会に根ざす組織や制度が脆弱であったことが指摘されている(伊藤 1997: 245)。実際,研究保存会の構成員からもかつてのK城隍祭は「体系的なものはないが家族的なもの」であり,道文化財指定と関連して「組織的なもの」や「体系的なもの」ができたという語りが聞かれた。つまり研究保存会は地域社会を背景にもつ組織である一方,文化財政策を反映し新たにたち現れたコミュニティであるといえる。
地域住民の積極的な参与がみられるマウルクッの場合であっても,民俗学者の関心や視線が宗教的職能者である巫者に偏る傾向にあることは先行研究でも指摘されている(浮葉2021)。伝承主体としての地域社会や保存会に対する視角は限定的であり,それぞれが内包する多様性や矛盾,葛藤は俎上にのらず一枚岩的なものとして把握される傾向にある。
発表者はこれまで 2020年・2021年のK城隍祭に参加し,地域住民による風物練習への参与観察や関係者(研究保存会会員・始興市郷土資料室職員・研究者)へのインタビュー調査をおこなった。そこで得られたデータを基に,K城隍祭にかかわる多様な主体を明らかにし,実践の歴史的経緯(研究保存会の成立・展開の過程)や保存会内部における相互作用の重層性の把握を試みる。その上で変貌をつづける当該社会の現在を描き出すために,その変化の一結果であり一要因ともいえる道指定文化財への選出の意味を考察したい。
参照文献
伊藤亜人1997「無形文化財」伊藤亜人編『もっと知りたい韓国1』弘文堂, pp.243-246.
浮葉正親2021「文化財指定と村祭りの変容──三角山都堂祭における「国行祭儀」の挿入をめぐって」『韓国・朝鮮文化研究会第22 回研究大会 発表資料』2021 年10 月23 日
辻大和「朝鮮王朝期日常生活での薬用植物の消費について」
本発表では薬用人蔘をはじめとする薬用植物が 16~19 世紀の朝鮮の両班家などでどのように消費されたのかについて報告する。
同時代の東アジアにおける、薬用人蔘をはじめとする薬用植物の生産拡大については川勝平太・濱下武志編『アジア交易圏と工業化』(リブロポート、1991 年)や山田慶児編『東アジアの本草と博物学の世界』上下(思文閣出版、1995 年)のような蓄積がある。また朝鮮における薬用人蔘の栽培については今村鞆『人参史』全7 巻(朝鮮総督府専売局、1934~1940 年)や姜万吉『朝鮮後期商業資本의 発達』(高麗大学校出版部、1973 年)のような蓄積がある。
以上のように朝鮮でも薬用人蔘の生産が進んだことが分かってきたが、流通や消費に注目されるようになったのは最近のことである。発表者はこれまで韓国での流通拡大について「近世以降韓国における薬用人蔘製品の流通について」大坪玲子・谷憲一編『嗜好品からみた社会」(春風社、2022 年)において論じたことがある。ただし朝鮮時代の日常生活での薬用植物の利用のされ方については十分に検討が出来なかった。
朝鮮時代には医食同源の考えのもとで薬用植物の日常生活での消費が拡大した可能性があるが、その内実には未解明な部分が多い。19 世紀以前の薬用植物の朝鮮における医療以外の日常消費はどのようなものであったのか、というのが本発表の主題である。そのために韓国国史編纂委員会等で収集され刊行されている両班などの日記史料を参照し、そのなかに現れる日常生活での薬用植物の利用のされ方について事例を集積するとともに、傾向などを分析する。具体的には柳希春の『眉岩日記』などのように日記中に多くの食材名が現れる史料を中心に事例収集を行う。
近年、韓国や日本での食生活については多くの研究蓄積が見られるが、主食や肉食、料理法などが主たる内容のものが多く、野菜、薬用植物についての研究はこれからの要素が多いように思われる。本研究はそうした研究史上の欠落を補うことも目的とする。
柳川陽介「朝鮮日報社の出版事業と文学史 1930 年代を中心として」
本報告では 1930 年代朝鮮日報社の展開した出版事業が、朝鮮文学史の形成に与えた影響について考察する。近代朝鮮における文学作品は、定期刊行物に掲載されることで読者を獲得したが、とりわけ1920 年に創刊された『東亜日報』と『朝鮮日報』の学芸面は、作品とその批評が行き交う媒体として重要な役割を果たした。新聞以外にも、文学者を志す一部の青年は同人誌をつくり自ら表現の場を設けたが、いずれも短命に終わった。その一方、1930 年代に入ると『新東亜』『中央』『朝光』など、潤沢な資本と販売網をもつ新聞社系列の月刊総合誌が相次いで登場し、安定して発行された。とりわけ1930 年代中盤に朝鮮日報社が発行した『朝光』(1935-45)『女性』(1936-40)『少年』(1937-40)には、時事関連の記事や評論と並び連載小説や短篇、詩、批評、童話など様々な文学作品が掲載された。このように、植民地期朝鮮文壇は日刊紙と月刊誌を中心に形成されたが、新聞社は両媒体を同時に発行していた点で注目される。
1930 年代後半の朝鮮日報社は、上記の定期刊行物以外にも様々な出版物を刊行した。なかでも『世界傑作童話集』(1936)、『現代朝鮮女流文学選集』(1937)、『現代朝鮮文学全集』(全七巻、1938)、『新選文学全集』(全四巻、1938-39)、『朝鮮名人伝』(全三巻、1939)、『世界名人伝』(全三巻、1940)など企画出版として刊行された書籍には、解放後の文学史において評価される作品が含まれているため、正典(canon)の形成に寄与したという指摘がある。先行研究では、個別の定期刊行物や全集毎に正典化の過程が解明されたが、朝鮮日報社の視点から接近した研究は、社史を含め本格的に行われていない。
そのため、本報告では朝鮮日報社と朝鮮文学史の関係について、以下の三点を中心に論じる。まず、鉱山経営で財産を築いた方應謨が、朝鮮日報社の経営権を獲得する過程で重視した人脈である。方應謨は李光洙、韓龍雲、洪命熹など名士の小説を連載することで購読者層の拡大を図る一方、自ら創設した奨学金制度を通じて白石、方鍾鉉、金起林、尹石重をはじめとする文学者の修学を支えた。こうした人脈と人材の育成が、学芸面の編集方針に与えた影響について考察する。次に、雑誌及び単行本の編集を担当した出版部と学芸部との関連性である。両部署は独立しており、学芸面の編集は洪起文と李源朝など学芸部の記者が担当していた。しかし、新聞や系列雑誌に掲載された作品を『新選文学全集』に収録する一方、関連した座談会を誌面で取り上げるなど、両者が相互補完の関係にあったことを確認する。最後に、近代文学史を作品で示した『現代朝鮮文学全集』と、朝鮮学研究の集大成である『朝鮮名人伝』を中心に、朝鮮日報社が出版事業を通じて「朝鮮」を可視化する様相を明らかにする。
(2) シンポジウム「「巫俗(シャーマニズム)」「迷信」再考」
川瀬貴也「趣旨説明」
朝鮮半島地域の文化研究において、巫俗(シャーマニズム)が重要な位置を占めていたことは言うまでもなかろう。外国人の研究としてはキリスト教の宣教師の「現地調査」がその端緒と言えるものだった。植民地期を代表する研究として、京城帝国大学の赤松智城・秋葉隆の『朝鮮巫俗の研究』(1937-38)があげられるが、この書では「女性を中心とする巫俗文化」と「男性を中心とする儒教文化」の二重構造が提示され、朝鮮女性の信仰世界を「巫俗」「道教」「仏教」のシンクレティズムとする見解が強調されている。朝鮮人学者たちも崔南善や李能化の研究を魁として、文化人類学、民俗学、宗教学、社会学など諸分野において巫俗を長年研究してきた。朝鮮半島の新宗教や、時にはキリスト教の分析においても「シャーマニックな特徴」は、ある意味「朝鮮文化の本質的なもの」として提示されてきたかも知れない。
一方巫俗は、近代初期から啓蒙主義者に攻撃、非難されたことも重要である。文化研究において巫俗は朝鮮民族の核をなすものと見なされがちではあったが、いわゆる「迷信」の中に巫俗はカテゴライズされた。別言すれば近代社会において、「まつろわざるもの」の代表でもある巫俗は、規律権力によって敵視され、取り締まられる対象であった。近代の洗礼を受けた朝鮮人の啓蒙思想家も「迷信」としての巫俗を攻撃したし、職能集団としてのムーダンも朝鮮王朝時代から社会的に低い地位に置かれた。そして巫俗を「宗教」よりも一段低いものと見なす近代的な学知の存在も見逃せない影響を持っていた。
しかし解放後も、例えばセマウル運動において「迷信打破」が高唱されようとも巫俗やシャーマニックな新宗教は決して無くならなかった。そして近年の韓国においては巫俗の祭祀(クッ)の保存会が設置されその維持が図られ、時には無形文化財指定を受け、一種の「文化ナショナリズム」の中核に置かれるなど、その扱いは大きく変容を遂げた。とは言え、韓国巫俗を無形文化財として語る場合、巫俗の「宗教性」、すなわち「迷信」的な側面が排除される傾向にあるとの指摘も重要であろう。要するに近現代朝鮮において巫俗は、「啓蒙の対象」であるのと同時に「民族文化の粋」として、両義的な意味を負わされてきたということである。
本シンポジウムでは「シャーマニズムこそ、朝鮮・韓国文化の本質である」というような本質主義的な立場を取らないが、その「持続性」に着目しつつ、近現代における変容と広がりを再確認したいと考えている。
古田富建「巫俗的韓国キリスト」の再考
これまで多くの研究者によって、「韓国のキリスト教は巫俗的である」という指摘がなされてきた。指摘の中身は、通声祈祷などの熱狂的な雰囲気、異言や病気治し(按手や按察)、逐邪行為を行う復興会、祈祷院、祈福信仰的な説教などである。さらに、ハレルヤ祈祷院、汝矣島純福音教会、キリスト教系新宗教のイエス教伝道館復興協会(現天父教)や世界基督教統一神霊協会(現父母様聖会)など、具体的な教会や教団も名指しされている。
そこで本発表では、発表者の「恨」言説研究の試みと照らし合わせて、「韓国のキリスト教は巫俗的である」を一つの言説として捉え直してみたい。それと同時に、韓国キリスト教空間に見られる宗教文化・宗教観を再定義する。この考察が、韓国でのキリスト教宣教の成功理由の解明の一助にもつながるものと考える。
始めに、「韓国のキリスト教は巫俗的」言説がどのように作られていくのかを時代区分で整理し、その特徴を考察する。具体的には、神学・巫俗研究者の柳東植を皮切りにしたキリスト教神学者、クリスチャンで巫俗研究者の崔吉城などが代表的な論者である。90 年代以降、秀村研二、渕上恭子などの日本での研究が続く。
二つ目に、「韓国のキリスト教は巫俗的である」という言説は、韓国の宗教空間は「儒教と巫俗の二重構造である」という見方を取り込みながら起きていると考える。韓国キリスト教の特徴を「父性的キリスト教/母性的キリスト教」「理のキリスト教/気のキリスト教」という図式的に捉えようとする言説はまさにそれであろう。
「儒教と巫俗の二重構造」は、「伝統社会」に見られた儒教文化と巫俗文化の二重性を述べたものであり、長く朝鮮半島の社会や文化を記述する枠組として指摘されてきた。昨今はこの「儒教と巫俗の二重構造」について批判的に見る眼差し(新里喜宣・ハンスンフンなど)も出てきている。これらの知見を踏まえて韓国キリスト教とその周辺にある宗教文化・宗教観の再定義を試みる。
三つ目に、韓国キリスト教の宗教空間を説明する新たな定義に基づき、巫俗的と指摘された韓国キリスト教について考察する。ここでは、導入期のキリスト教、戦後のキリスト教、世界基督教統一神霊協会(現父母様聖会)、イエス教伝道館復興協会(現天父教)とその系譜団体を取り上げる。
新里喜宣「巫俗は「宗教」か、「宗教ではない宗教」か―祈福信仰、宗教概念、普遍的価値観という桎梏―」
韓国において巫俗への多様な視点が台頭し始めた 1960 年代以降、巫俗は迷信として否定的に捉えられつつ、文化として肯定的な価値も付与されることになった。発表者が既存の論文で発表してきたように、「巫俗の占いは迷信だが、踊りや音楽は文化」などの形式で、巫俗を文化として認める言説が生産され、それがひろく流布し、クッや巫楽を国家無形文化財として登録する動きも進んでいった。
これを踏まえて、本発表では巫俗を「宗教」と捉える言説に注目したい。ムーダンと信者によって構成される巫俗の信仰や儀礼としての側面は、音楽や踊りなどの文化的領域と比べると軽視されてきたことは否めない。巫俗について語った多くの論者は、巫俗の宗教的領域を「祈福信仰」の一言で切り捨て、巫俗は文化としては認められるが、宗教としての価値はないと判断してきた。
他方、土着化神学や民衆神学を専攻する研究者、また、民俗学者の一部は、祈福性は宗教全般に基本的に見られる特徴であって、それ自体は巫俗を宗教ではないと判断する基準にはなり得ないと主張した。そこで彼らは巫俗の宗教的側面に対する思索を深め、クッに見られる共同体意識、ムーダンと信者の情熱的な信仰などを宗教として認める視点を打ち出した。このような言説は巫俗を部分的に宗教の領域に含めるものであり、巫俗の文化的側面にのみ注目する言説とは性格を異にするものであった。
ただ、巫俗を宗教の領域に含めようとする際、次なる障壁として立ちふさがったのが「宗教」概念であった。主にキリスト教をモデルとする宗教概念によって、宗教には倫理意識、歴史意識、共同体意識、いわば普遍的価値観が求められるとされ、巫俗にはこれらが欠如していると見なされた。たとえば、巫俗の関心は基本的に家族にのみ向いており、人類という単位には関心が向けられていないとされ、これが普遍的価値観の不在として捉えられたのである。ここで、巫俗を不完全な宗教、すなわち「宗教ではない宗教」とする巫俗認識が成立することになった。1960 年代以降、巫俗が宗教としても一部再考の対象になったことは事実だが、詳細に検討してみると、それらの言説の大部分がこの「宗教ではない宗教」としての巫俗認識を支持していたことが確認できる。
反面、1960 年代から 1980 年代において、一部の神学者が巫俗は宗教と見なせると判断したことも事実である。また金泰坤や趙興胤などの民俗学者は、巫俗にも普遍的価値観が見出されると主張し、彼らは巫俗を宗教として押し出す言説を生産していった。巫俗を「宗教ではない宗教」としてではなく、「宗教」と捉えた主体の論理はどのようなものであったのか。本発表では最後に金泰坤や趙興胤などの言説も確認し、彼らの言説がもつ意味を考えてみたい。
影本剛「迷信、あるいは生の原動力 ――近代朝鮮文学とジェンダーの問い」
本発表は植民地朝鮮とその前後における朝鮮文学において、いかに迷信(的なもの)が描かれたかを検討するものだ。朝鮮文学と迷信の関係を単純化して整理すれば、1920 年代までは「前近代的なもの」として迷信は批判対象になり続けたが、1930 年代に入ってから崔南善の評論や金東里の小説によって「朝鮮的なもの」という新しい意味が付与されたということができる(先行研究もこの視角から検討するものが多い)。
しかし本発表は、そのような最初から意味付けされた迷信を描く文学に注目するのではなく、無数の作品に登場する背景に描かれる迷信の描かれ方を収集し、それをジェンダーの問いから並べ直す作業を試みた。発表者が文学資料から読みとったものは、第一に近代医療に敵対するものとしての迷信、第二に近代社会において発言者として認められない女性たちが社会的に発言する方法としての迷信、第三に生の原動力としての迷信である。
1,近代医療に敵対するものとしての迷信は、近代的医療であれば治療可能だったにもかかわらず迷信で治療をしようとしたがために患者が死んでしまう情景を小説から集めた。
これは民衆世界に自然科学の知が届いていないことを何度も繰り返し描くものであり、啓蒙の視線が重なる。作品としては廉想渉「万歳前」、蔡萬植『濁流』、李箕永「鍛冶屋」『大地の息子』などを検討する。
2,女性が社会的発言をする方法としての迷信は、社会において女性の発言権がない場合、女性の声が迷信として現れるという情景を小説から集めた。これは現代文学のチョ・ナムジュ『82 年生まれ、キムジヨン』でも反復される。作品としては李光洙「無情」(短編)、羅稲香「夢」、李箕永「間隙」「陣痛期」、韓雪野『塔』、鄭人澤「清涼里界隈」などを検討する。
3.生の原動力としての迷信は、将来の展望が消える時に、生の根拠となり、生の原動力となる迷信を描く小説を集める。作品としては金南天『大河』、廉想渉『驟雨』などを検討する。『大河』では離婚と新しい恋愛の決断という瞬間に、『驟雨』では朝鮮戦争下で生きる根拠を確保するために迷信が登場するのだ。ここでも迷信と関わり生の原動力を見出すのは女性たちである。
以上の三点はそれぞれジェンダーの問いと関連している。発表では、これらを文学作品に現れた具体的な情景を整理・検討することで、近代朝鮮文学と迷信の関係に問題提起をするものである。
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内