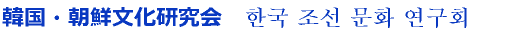![]()
韓国・朝鮮文化研究会会員各位
開催方式につきましては,昨今の情勢を踏まえ,対面とオンラインの併用としました。
記
韓国・朝鮮文化研究会第24回研究大会
日時:2023年10月14日(土) 10:30~17:30
開催方式:対面とオンラインの併用
・対面会場:横浜国立大学 S2-1 都市科学部講義棟102
交通アクセス:https://www.ynu.ac.jp/access/
施設案内:https://www.ynu.ac.jp/access/map_campus.html
※都市科学部講義棟は大学正門に近く,横浜駅西口バスターミナルより相鉄バス「浜5」系統乗車,岡沢町で下車数分の距離です(土曜日は構内直通バスがありません)。または横浜市営地下鉄ブルーライン三ッ沢上町駅から徒歩20分程度です。会場は羽沢横浜国大駅からは離れた立地です。
・オンライン会場:Zoom会議室
□ プログラム
10:10対面受付・オンライン入室開始
10:30~12:00 一般研究発表
羅孟晋「「伝統」へ「回帰」する余生─現代韓国郷校儒林の歴史的な自分探し」
阪堂博之「京城における政治空間へのメディア参入の背景-1920年代の東亞日報を中心に」
12:00~12:50 昼休み
12:50~13:20 会員総会
13:30~17:30 シンポジウム「韓国家族再考──制度/イデオロギーと実践の脱家族的相対化に向けて」
趣旨説明:本田洋
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
コメント:川口幸大・古田富建
総合討論
18:45 懇親会(要事前申込)
京華樓 鶴屋町CRANE店にて
□発表・報告要旨
(1)一般研究発表
羅孟晋「「伝統」へ「回帰」する余生─現代韓国郷校儒林の歴史的な自分探し」
民主化以降の韓国研究における重要なテーマとして,伝統とナショナリズムあるいは消費主義との結合で生じた「伝統の発明」や「伝統の消費」という社会動向が,これまで多くの研究者によって論じられてきた。その一方で,韓国の地域社会における儒教組織の研究では,「地方主義」や「身分上昇志向」などの文化事象が儒教伝統との関連で検討されてきた。これに対し,本発表で扱う産業化世代の「郷校儒林」の社会実践は,この二つの論議の交差点に位置づけられるものの,先行研究での論議と相当異なるあり方を示している。彼ら・彼女らは職場生活を終えた後,数年から二十年余りにわたって古色蒼然たる郷校に定期的に出入りする。そこで儒学伝承や郷校運営の責任を担い,また教育活動と文化行事を通して緩やかな共同体を築く。その社会実践には,先行研究が注目してきた政治経済的な目的よりも,実践者自身の感情や倫理および記憶との複雑な絡み合いが際立つ。
1990年代以降,儒教組織の周縁化が強まった都市社会において,激しい宗教的かつ政治的葛藤を経験した郷校儒林は,それまで排斥されていた他宗教の信者や女性を儒教組織に包摂し始めた。産業化世代の郷校儒林は,成均館の「宗教化」傾向を回避する一方で,韓国人が共有する「伝統」を学ぶという価値を打ち出し,学びの共同性を創出している。その過程で,儒教組織としての実践目標が,次第に他者規律から自己規律へと移行し,さらに「精誠」という美徳の我有化に絞り込まれるようになった。その「精誠」とは,他者への誇示を通じて福や威信を獲得することではなく,主に漢文の学習と「礼」のパフォーマンスを通じて喚起される目くるめく意味世界で,自らの「心の醇化」として体験されるものとみることができる。とりわけ「伝統」の学習を通じて自己の「精誠」を引き出す倫理実践と,儒教組織に献身する社会実践との間には,家族に関わるさまざまな辛い記憶が普遍的に介在し,両者をつなげる動機となっている。すなわち,都市社会の日常から離れ,「伝統」をめぐる意味世界を流れる歴史にもたれかかったその「回帰」実践は,一部の高齢者にとって,産業化以降の激変ゆえに矛盾を生じた記憶と自己を整える主体化過程をなすといえる。
この発見を踏まえ,本発表では2021年に調査した水原郷校の事例を取り上げ,倫理的主体化という視点から現代「郷校儒林」の社会実践を民族誌的に考察する。まず産業化世代の高齢者が老後の生活で都市の儒教組織に身を投じる社会実践の意味と論理を明らかにする。それと同時に,「伝統」へ「回帰」する社会実践から紡ぎ出される意味世界の解釈を通じて,現代韓国社会における儒教と「伝統」を理解する視座を再検討したい。
阪堂博之「京城における政治空間へのメディア参入の背景-1920年代の東亞日報を中心に」
ソウル中心部の光化門前は韓国の政府庁舎やソウル市庁舎などの官公庁、外国の大使館などが集中し「政治空間」を形成している。同時に、その中に大手紙の『東亞日報』『朝鮮日報』『ソウル新聞』などが本社を置き、東京では見慣れない風景をつくり出している。政治空間の中にメディアが存在するという風景は1926年10月、植民地朝鮮の中心都市京城において、景福宮内に朝鮮総督府庁舎が竣工し、同年12月、光化門交差点に『東亞日報』が社屋を移転した時に原形が出来上がったといえる。ソウルの政治空間へのメディアの参入は植民地時代に始まった。
『東亞日報』は1919年の「3・1独立運動」を受けた「文化政治」期の1920年に創刊された代表的な民族紙(朝鮮語紙)である。当時、『東亞日報』は朝鮮総督府の新庁舎建設地を知った上で新社屋の移転先として光化門前を選択した。その経緯や意図の分析を通じて、植民地朝鮮において民族紙がどのような存在として位置付けられていたのかを考察する。
『東亞日報』は創刊当初、景福宮の東側に位置する鍾路区花洞にある瓦葺きの韓屋を社屋として使用した。当然ながら新聞社の社屋としては手狭で、1924年春から社屋移転に向けて本格的に動き出した。臨時役員会での協議を経て社屋移転先として「光化門139番地」(世宗路)に400余坪の土地を購入した 。移転先は臨時役員会でもなかなか決まらなかったが、社主の金性洙の意向によって光化門交差点と決定した。
金性洙は光化門前を選んだ理由として①朝鮮民族および朝鮮王朝の伝統的精神を守る②日本および朝鮮総督府の野望を防いで監視し朝鮮民族の烽火(のろし)台の役割を果たす-ことを挙げた。②は民族ジャーナリズム本来の役割を強調したものといえるが、①で光化門前への社屋移転によって朝鮮王朝の伝統的精神を守らねばならないと強調している点は注目に値する。
これらは金性洙が民族紙をどのように位置付けようとしていたかを示している。金性洙のこうした見解には、当時の植民地朝鮮の市民にとって民族紙がいかなる存在だったのか、民族紙がどう認識されていたのかが反映されていると考えられる。
(2)シンポジウム「韓国家族再考──制度/イデオロギーと実践の脱家族的相対化に向けて」
本田洋「趣旨説明」
このシンポジウムでは,韓国の家族の現在とその歴史的構築について,制度/イデオロギーと生の実践の双方向的関係に着目して再検討を試みる。すなわち,家族と関わる社会慣習や国家の法・政策,ならびに家族のあり方に関する観念・論理・イデオロギーが人びとの生の営みにどのように関係づけられるのか,またこのような制度/イデオロギーが,日常生活から大衆文化(例えば歌謡やドラマ・映画),啓蒙的言説・形象(例えばマスメディア,ネットメディア,出版・刊行物,博物館),宗教,社会科学的思考,さらには法・政策論議に至るまでの社会文化的諸領域で,どのように交渉され形づくられるのかになるべく広く目配りしつつ,韓国の家族を再照査したい。これを通じて,「家族」の指示する社会文化的諸事象のより精緻な理解と,概念装置としての「家族」の相対化──その当為性・自明性の問い直しをも含めた脱家族的相対化──を目論むものである。朝鮮近代史(田中美彩都氏),人類学(澤野美智子氏),福祉社会学(株本千鶴氏)を専門とする三氏の報告に加え,川口幸大氏(人類学・漢族研究)と古田富建氏(宗教学)に討論者として登壇していただき,フロアからの参加も含め,韓国家族の現在と歴史的構築について様々な角度から論じたい。
報告題目
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
以下,多少長くはなるが,この趣旨設定の背景を説明しておこう。まず起点として,「家族」という概念装置が近代的な構築物であること,あるいは在来の制度/イデオロギーや諸実践が「家族-family」という近代的な外来の概念との接合によって不断に再構築を迫られてきたことを指摘したい。このような概念装置とは,すなわち「家族」(kajok)という日常語/学術用語やそれに含意されるfamily/home/householdといった諸観念の指示する様々な集団や関係性の枠組みを用いて,現実を認識・言語化し,関係を交渉し,相互行為を生み出してゆくような思考,表象と実践の習慣の意である。保護国期から植民地期にかけての啓蒙的言説では,在来の「大家族」・「家族制度」が批判され,「父子各居」の「小家族」・「単式家族制度」や「一夫一婦とその子女」だけを含む「家庭」が想像されるなど,当時の現実と欧米や日本から伝えられた「家族-family」概念を接合・対照しつつ,その開化的,理想的なあり方が論じられていた。同じく「民籍」・「戸籍」をめぐる法制度の編成過程では,現実の生活集団や扶養関係(戸主と「食口」)と父系血統として構築された「慣習」,さらには日本から導入が試みられた家制度が相互対照され,非血縁者を含む広義の扶養関係にある者たちの身分関係や家族的な集団が法的に再定義されていった。ここに制度/イデオロギーと実践の双方向的関係を見出すこともできよう。
もう一点,特に実践としての家族を考えるにあたって念頭に置くべきは,この近代的構築物である「家族」が,「民籍」に関する法的議論のひとつの論点ともなっていたように,①同じ「チプ」(住居)に暮らす生活集団あるいは扶養関係と,②拡大的な父系親族の,二重の意味を担わされていた点である(cf. 金斗憲 1969(初版1949) 『韓国家族制度研究』)。解放後の家族研究史は,実際,この二重性の展開としても捉えうる。
1950年代以降に本格化する韓国農村社会を対象とした社会学・人類学的研究では,同じチプ(住居)に暮らし,基本的な生計を共にし,さらには生産・経済活動の基本単位ともなる近親者の集団を経験的に「家口」(世帯household)として再定義し,その境界を越えた近親間の依存・協力関係や父系親族の組織化と関連付けながら,その構成や役割・機能(社会構造的諸側面)について実地調査や統計調査に基づいた詳細な分析を行った。これに対し,産業化過程での農村社会の変化と都市的生活領域の形成に関する人類学・民族誌的研究や,植民地期にまで遡るオーラル・ヒストリーを主たる資料とする歴史民族誌的研究では,階級・階層やその他の社会経済的諸条件によって異なる様相を示す父系/非父系の近親者間の依存・協力関係と「家口」の編成を,集団/関係としての家族を一つの資源として活用する生計維持や社会上昇の戦略的・交渉的な諸実践として捉え直した。これは近代核家族理論への批判的視座を提起するものでもあった。このうちフェミニスト/ジェンダー人類学的な観点が強く表れる都市中産層の民族誌では,資本主義的労働市場で主たる「生計扶養者」となった夫・父親によって担われないあらゆる役割を引き受けるようになった妻・母親の交渉的実践と行為主体性,特に母性に注目が集まった。「専業主婦」として自己同定する彼女たちの役割は,家事・庶務,子供の養育と教育管理から,インフォーマルな経済・利殖活動と誇示的消費,さらには近親者との関係管理にまで及ぶ。
冒頭に述べた実践への制度/イデオロギーの複雑な介在という論点は,後者のような家族の再生産戦略に焦点を合わせた諸論考ですでに提示されていた。これを双方向的・相互作用的な過程に位置づけるにあたっては,多様な,時に競合する様々な「家族主義」の構築や,「家父長制」と総称される「家口」内部や近親者間の微視的な権力関係の再生産をめぐる議論が参考になるかもしれない。
近代家族を論ずる家族社会学・フェミニスト社会学や認知・行為モデルを論ずる文化人類学では,「家族」の実践に介在する社会規範,状況的合理性・実践的論理,あるいは国家・市場制度の原理を,しばしば「家族主義」(familism)という融通無碍な概念で対象化し,時に「家父長制」と関連付けて論ずる。例えば,農村社会の歴史民族誌で指摘されていたような,生活の必要性に促された依存・協力関係(実践的諸関係)といわゆる伝統的家族・親族理念(公式的親族)との齟齬や両者の折衝を通じた状況的合理性・実践的論理の構築は,「功利的・道具的家族主義」と「道徳的・理念的家族主義」との対立,ならびに「状況的家族主義」への止揚と捉えることができよう。産業化過程で形成された都市中産層夫婦家族をめぐる役割関係・性別分業や情緒性・親密性は,「儒教的家父長制」の「家父長制的資本制」への接合として論じられる(これを「新家族主義」と呼ぶ研究者もいる)。また,後期近代におけるリスク社会化と福祉レジームの再編成を論ずる近年の社会学では,社会の基本的な構成単位の「個人化」や個への志向性と人びとを強く拘束する諸々の「家族主義」との複雑な関係や,福祉制度の原理としての複数の「(制度的)家族主義」の可能性が論じられるようになっている。
このような「家族主義」・「家父長制」論からも垣間見えるように,現代韓国社会における概念装置としての「家族」の作用は,家族の現実とそれを論ずる社会科学的視角や啓蒙的言説,多様なメディアに媒介された表象,さらには法・政策論議が複雑かつ再帰的にもつれ合う状況をも呈しているのだと考えられる。このシンポジウムでは,家族をめぐる制度/イデオロギーの構築を腑分けしつつ,諸々の「家族主義」やその他の文化的レパートリーが家族の実践・交渉にどのように介在させられるのかを明らかにすることによって,韓国家族の現実へのより精緻な理解を試みたい。
最後に,概念装置としての「家族」の相対化に向けて,一つの手がかりを示しておこう。朝鮮・韓国社会における近代的な「家族」概念に含意されていた生活集団・扶養関係と父系血統の重なり合いとずれは,構造機能論では「家口」と家族・親族の相補性として読み替えられ,さらに農村社会の歴史民族誌的研究では実践的諸関係と公式的親族の弁証法的関係として分析し直された。この重なり合いとずれは,近年の韓国社会においても,血縁を主要な原理として制度化された近代家族ならびにそれを支える結婚制度と,制度的家族にとって過重な負荷となっているケア(養育・扶養など)の諸関係との齟齬(少子化・晩婚化・非婚・離婚などの形での顕在化)へと,位相を変えて再生産されているのではないか。なぜ制度的に規定された特定の近親者がケアの責任を担わなければならないのか。なぜパートナー間の分業や親密性,あるいは親子の扶養関係や情愛が,社会的/法的な結婚制度によって認証を受けなければならないのか。「家族」の当為性や自明性自体をも問い直すことで,一方でエミックな(当事者にとっての)/他方でエティックな(研究者にとっての)概念装置としての「家族」の脱家族的相対化を試みたい。
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
本報告では、近代(保護国期から植民地期)の朝鮮半島における、養子制度を中心に、韓国「儒教社会論」の下地としての家族「伝統」が形成される過程を明らかにしたい。統監府期に設置された法典調査局は1908~1910年にかけて、梅謙次郎の指揮のもとで家族をふくむ民事に関わる慣習をインタビュー・古文献により調査した。また1910年の民籍法施行に伴い、担当官署である警務局は各戸を網羅的に調査した。
法典調査局の調査結果は、植民地化後に『慣習調査報告書』(朝鮮総督府、1910・1912・1913年)として整理された。さらに1912年に制定された朝鮮民事令はその第11条で朝鮮人の親族・相続は「慣習」によることを定めた。以降は植民地政府が「慣習」と認めた内容が、朝鮮人の家族のありようを法的に規定することになる。
朝鮮の養子「慣習」は異姓不養、すなわち儒教祭祀を摂行可能な父系血統を同じくする同姓の男子のみに限ることとされた。しかし少なくとも統監府期の慣習調査時の資料や新聞記事などからは、多くの地域で、高麗時代以来の慣行である異姓を対象とした収養子も認められていたことがわかる。しかもその定義は、「食口」から祖先祭祀の摂行者に至るまで、地域や階層ごとに多様であった。
収養子は全人口の登録を最優先課題とした民籍に当初そのまま登録されたが、1916年、朝鮮総督府は「慣習」に則り収養子の民籍登録を禁止する。その結果、異姓養子縁組は法的な庇護を得られなくなった。異姓養子により家系を継承してきた宦官家や、民籍で養父子として登録された僧侶と上佐(弟子)の関係性も影響をこうむった。
なお、朝鮮総督府が異姓不養を「慣習」とみなした背景には、法典調査局の慣習調査に回答した儒学教養をもつ地域の指導層が調査者に理想とする家族像を強調したこと、『経国大典』『大明律直解』などの古文献調査の結果がこうした証言に信ぴょう性を与えた可能性を指摘しうる。一方女性の権利拡大を訴える朝鮮人知識人は儒教に基づく父系血統重視の家族制度の否定を「近代化」への道筋ととらえたが、1939年の朝鮮民事令改正による異姓養子の合法化から解放後韓国の民法典編纂に至る過程で、異姓不養を含む父系血統主義が「伝統」と名指されるようになったことも見逃せない。
つまり儒教化したとされる朝鮮後期以降の社会でも父系血統に基づかない多様な家族のありようが許容されていたが、統監府・朝鮮総督府が認定した「慣習」と韓国朝鮮社会が時代状況にあわせて求めてきた理想的な家族像が相互に作用しあうことで、儒教的な父系血統を重要視する「伝統」が生み出されたといえよう。
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
家族の「理想像」は時代や場所によって異なるが、それぞれの形で存在し、人々は意識的・無意識的にそこから影響を受けていると考えられる。「理想像」のような家族を築こうとしたり、「理想像」を実現したいのにできなくて苦悩したり、逆に敢えて「理想像」とは異なる生き方を積極的に選択したりもする。
韓国の場合、儒教思想における家族規範、植民地時代や解放後の法制度における家族、西洋的な近代家族など、社会変化に伴って家族の様々な「理想像」が混在しつつ目まぐるしく変化してきた。1世代異なれば家族の「理想像」も異なるような状況下、西洋的な家族の〈模倣〉をしながら儒教的な家族の〈模倣〉も並行するというように、人々は複数の「理想像」の間で折り合いをつけ、あるいはそれらを組み合わせ、臨機応変に〈模倣〉を実践しながら家族を形成してきた。
しかしそれらは必ずしも常に調和していたわけではない。人々は複数の「理想像」の間で苦悩を抱えることもある。発表者が韓国で聞き取りを行なってきた乳がん患者たちの語りにおいても、病気に罹った原因として語られる家族の問題には、そのような複数の「理想像」の狭間で苦悩する女性たちの姿が浮かび上がる。それは時には自分が理想とする家族と、自分の親世代が理想とする家族、あるいは自分の子世代が理想とする家族との間の狭間である。また時には、自分が実現したい家族の「理想像」と、その実現を阻んだり家族規範を逸脱したりする家族成員との間の狭間である。
一方で現代韓国社会においては、家族の様々な「理想像」が根強く存在しつつも、家族形態の〈模倣〉に執着するより合理性を優先することが珍しくなくなっている。例えば急速に進行する少子化に見られるように、家族の「理想像」を〈模倣〉しなくていい自由と、自らの意志と責任でライフスタイルを作り上げていかねばならない試行錯誤の時代を、人々は生きていると言えよう。
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
本報告は、韓国におけるケア提供システムと家族主義の関係について考察するものである。ケアのなかでも介護(主に高齢者対象)と看病をとりあげ、それらを対象とした制度・政策および実践と家族主義の関係、そして、それらが目的とする介護・看病の社会化の現状について検討したい。
韓国の社会福祉や社会保障、社会政策を対象とした研究では、ケア提供システムが家族主義から強い影響をうけていることが明らかにされている。ここで用いる家族主義は、社会学者の金東椿が家族主義の類型のひとつとしてあげている「制度的家族主義」とほぼ同義である。「制度的家族主義」とは、「保育、高齢者介護、福祉などを国家や社会が担当するよりも家族が優先的に担当すべきであるとする思考や、そのような思考や慣行から作られた福祉、介護などの家族依存的な法・制度」をさす。
制度的家族主義は、現実の家族介護および看病の担当者に過重な負担を強いている。その負担を軽減するために支援策が実施されているが、成果はあまりあがっていない。
たとえば老人長期療養保険制度は、その目的のひとつを「家族負担の軽減」、すなわち介護の「脱家族化」としている。しかし、インフラ不足改善のために作られた「家族療養給付」は、介護の「家族化」を促す要素となっている。「家族療養給付」は、資格をもつ療養保護士が利用者である家族を介護した場合に介護報酬を給付するものであるが、訪問療養受給者の約20%が家族である療養保護士から介護をうけている(2020年1月)。家族療養保護士による介護には長所もあるが、不正受給やケアの点検・管理の困難という短所もある。看病にかんしても、たとえば、看病人(付添い)の雇用が患者家族の重い負担になっているが、これに対する支援策も看病の「脱家族化」を顕著に進展させるほどの成果をあげていない。
報告では、上記のような介護と看病を対象とした制度・政策および実践と家族主義の関係、そして、介護と看病の社会化の現状について検討したのち、ケアの社会化の今後についても考えてみたい。ケアに関する問題が以前よりも重視される現代韓国社会では、ケアに関する社会的権利、あるいは、ケアの社会的保障の確立をめざす研究や活動が活発化している。一方で、ケアの家族化を維持・強化する、ケアサービスの産業化や孝行奨励・支援制度の実施などがある。これらの社会的事実によって「制度的家族主義」がどの程度変容するかが、ケアの社会化の今後のあり方に関わってくるであろう。
以上
開催方式につきましては,昨今の情勢を踏まえ,対面とオンラインの併用としました。
韓国・朝鮮文化研究会
第24回研究大会委員長
辻 大和
第24回研究大会委員長
辻 大和
韓国・朝鮮文化研究会第24回研究大会
日時:2023年10月14日(土) 10:30~17:30
開催方式:対面とオンラインの併用
・対面会場:横浜国立大学 S2-1 都市科学部講義棟102
交通アクセス:https://www.ynu.ac.jp/access/
施設案内:https://www.ynu.ac.jp/access/map_campus.html
※都市科学部講義棟は大学正門に近く,横浜駅西口バスターミナルより相鉄バス「浜5」系統乗車,岡沢町で下車数分の距離です(土曜日は構内直通バスがありません)。または横浜市営地下鉄ブルーライン三ッ沢上町駅から徒歩20分程度です。会場は羽沢横浜国大駅からは離れた立地です。
・オンライン会場:Zoom会議室
□ プログラム
10:10対面受付・オンライン入室開始
10:30~12:00 一般研究発表
羅孟晋「「伝統」へ「回帰」する余生─現代韓国郷校儒林の歴史的な自分探し」
阪堂博之「京城における政治空間へのメディア参入の背景-1920年代の東亞日報を中心に」
12:00~12:50 昼休み
12:50~13:20 会員総会
13:30~17:30 シンポジウム「韓国家族再考──制度/イデオロギーと実践の脱家族的相対化に向けて」
趣旨説明:本田洋
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
コメント:川口幸大・古田富建
総合討論
18:45 懇親会(要事前申込)
京華樓 鶴屋町CRANE店にて
□発表・報告要旨
(1)一般研究発表
羅孟晋「「伝統」へ「回帰」する余生─現代韓国郷校儒林の歴史的な自分探し」
民主化以降の韓国研究における重要なテーマとして,伝統とナショナリズムあるいは消費主義との結合で生じた「伝統の発明」や「伝統の消費」という社会動向が,これまで多くの研究者によって論じられてきた。その一方で,韓国の地域社会における儒教組織の研究では,「地方主義」や「身分上昇志向」などの文化事象が儒教伝統との関連で検討されてきた。これに対し,本発表で扱う産業化世代の「郷校儒林」の社会実践は,この二つの論議の交差点に位置づけられるものの,先行研究での論議と相当異なるあり方を示している。彼ら・彼女らは職場生活を終えた後,数年から二十年余りにわたって古色蒼然たる郷校に定期的に出入りする。そこで儒学伝承や郷校運営の責任を担い,また教育活動と文化行事を通して緩やかな共同体を築く。その社会実践には,先行研究が注目してきた政治経済的な目的よりも,実践者自身の感情や倫理および記憶との複雑な絡み合いが際立つ。
1990年代以降,儒教組織の周縁化が強まった都市社会において,激しい宗教的かつ政治的葛藤を経験した郷校儒林は,それまで排斥されていた他宗教の信者や女性を儒教組織に包摂し始めた。産業化世代の郷校儒林は,成均館の「宗教化」傾向を回避する一方で,韓国人が共有する「伝統」を学ぶという価値を打ち出し,学びの共同性を創出している。その過程で,儒教組織としての実践目標が,次第に他者規律から自己規律へと移行し,さらに「精誠」という美徳の我有化に絞り込まれるようになった。その「精誠」とは,他者への誇示を通じて福や威信を獲得することではなく,主に漢文の学習と「礼」のパフォーマンスを通じて喚起される目くるめく意味世界で,自らの「心の醇化」として体験されるものとみることができる。とりわけ「伝統」の学習を通じて自己の「精誠」を引き出す倫理実践と,儒教組織に献身する社会実践との間には,家族に関わるさまざまな辛い記憶が普遍的に介在し,両者をつなげる動機となっている。すなわち,都市社会の日常から離れ,「伝統」をめぐる意味世界を流れる歴史にもたれかかったその「回帰」実践は,一部の高齢者にとって,産業化以降の激変ゆえに矛盾を生じた記憶と自己を整える主体化過程をなすといえる。
この発見を踏まえ,本発表では2021年に調査した水原郷校の事例を取り上げ,倫理的主体化という視点から現代「郷校儒林」の社会実践を民族誌的に考察する。まず産業化世代の高齢者が老後の生活で都市の儒教組織に身を投じる社会実践の意味と論理を明らかにする。それと同時に,「伝統」へ「回帰」する社会実践から紡ぎ出される意味世界の解釈を通じて,現代韓国社会における儒教と「伝統」を理解する視座を再検討したい。
阪堂博之「京城における政治空間へのメディア参入の背景-1920年代の東亞日報を中心に」
ソウル中心部の光化門前は韓国の政府庁舎やソウル市庁舎などの官公庁、外国の大使館などが集中し「政治空間」を形成している。同時に、その中に大手紙の『東亞日報』『朝鮮日報』『ソウル新聞』などが本社を置き、東京では見慣れない風景をつくり出している。政治空間の中にメディアが存在するという風景は1926年10月、植民地朝鮮の中心都市京城において、景福宮内に朝鮮総督府庁舎が竣工し、同年12月、光化門交差点に『東亞日報』が社屋を移転した時に原形が出来上がったといえる。ソウルの政治空間へのメディアの参入は植民地時代に始まった。
『東亞日報』は1919年の「3・1独立運動」を受けた「文化政治」期の1920年に創刊された代表的な民族紙(朝鮮語紙)である。当時、『東亞日報』は朝鮮総督府の新庁舎建設地を知った上で新社屋の移転先として光化門前を選択した。その経緯や意図の分析を通じて、植民地朝鮮において民族紙がどのような存在として位置付けられていたのかを考察する。
『東亞日報』は創刊当初、景福宮の東側に位置する鍾路区花洞にある瓦葺きの韓屋を社屋として使用した。当然ながら新聞社の社屋としては手狭で、1924年春から社屋移転に向けて本格的に動き出した。臨時役員会での協議を経て社屋移転先として「光化門139番地」(世宗路)に400余坪の土地を購入した 。移転先は臨時役員会でもなかなか決まらなかったが、社主の金性洙の意向によって光化門交差点と決定した。
金性洙は光化門前を選んだ理由として①朝鮮民族および朝鮮王朝の伝統的精神を守る②日本および朝鮮総督府の野望を防いで監視し朝鮮民族の烽火(のろし)台の役割を果たす-ことを挙げた。②は民族ジャーナリズム本来の役割を強調したものといえるが、①で光化門前への社屋移転によって朝鮮王朝の伝統的精神を守らねばならないと強調している点は注目に値する。
これらは金性洙が民族紙をどのように位置付けようとしていたかを示している。金性洙のこうした見解には、当時の植民地朝鮮の市民にとって民族紙がいかなる存在だったのか、民族紙がどう認識されていたのかが反映されていると考えられる。
(2)シンポジウム「韓国家族再考──制度/イデオロギーと実践の脱家族的相対化に向けて」
本田洋「趣旨説明」
このシンポジウムでは,韓国の家族の現在とその歴史的構築について,制度/イデオロギーと生の実践の双方向的関係に着目して再検討を試みる。すなわち,家族と関わる社会慣習や国家の法・政策,ならびに家族のあり方に関する観念・論理・イデオロギーが人びとの生の営みにどのように関係づけられるのか,またこのような制度/イデオロギーが,日常生活から大衆文化(例えば歌謡やドラマ・映画),啓蒙的言説・形象(例えばマスメディア,ネットメディア,出版・刊行物,博物館),宗教,社会科学的思考,さらには法・政策論議に至るまでの社会文化的諸領域で,どのように交渉され形づくられるのかになるべく広く目配りしつつ,韓国の家族を再照査したい。これを通じて,「家族」の指示する社会文化的諸事象のより精緻な理解と,概念装置としての「家族」の相対化──その当為性・自明性の問い直しをも含めた脱家族的相対化──を目論むものである。朝鮮近代史(田中美彩都氏),人類学(澤野美智子氏),福祉社会学(株本千鶴氏)を専門とする三氏の報告に加え,川口幸大氏(人類学・漢族研究)と古田富建氏(宗教学)に討論者として登壇していただき,フロアからの参加も含め,韓国家族の現在と歴史的構築について様々な角度から論じたい。
報告題目
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
以下,多少長くはなるが,この趣旨設定の背景を説明しておこう。まず起点として,「家族」という概念装置が近代的な構築物であること,あるいは在来の制度/イデオロギーや諸実践が「家族-family」という近代的な外来の概念との接合によって不断に再構築を迫られてきたことを指摘したい。このような概念装置とは,すなわち「家族」(kajok)という日常語/学術用語やそれに含意されるfamily/home/householdといった諸観念の指示する様々な集団や関係性の枠組みを用いて,現実を認識・言語化し,関係を交渉し,相互行為を生み出してゆくような思考,表象と実践の習慣の意である。保護国期から植民地期にかけての啓蒙的言説では,在来の「大家族」・「家族制度」が批判され,「父子各居」の「小家族」・「単式家族制度」や「一夫一婦とその子女」だけを含む「家庭」が想像されるなど,当時の現実と欧米や日本から伝えられた「家族-family」概念を接合・対照しつつ,その開化的,理想的なあり方が論じられていた。同じく「民籍」・「戸籍」をめぐる法制度の編成過程では,現実の生活集団や扶養関係(戸主と「食口」)と父系血統として構築された「慣習」,さらには日本から導入が試みられた家制度が相互対照され,非血縁者を含む広義の扶養関係にある者たちの身分関係や家族的な集団が法的に再定義されていった。ここに制度/イデオロギーと実践の双方向的関係を見出すこともできよう。
もう一点,特に実践としての家族を考えるにあたって念頭に置くべきは,この近代的構築物である「家族」が,「民籍」に関する法的議論のひとつの論点ともなっていたように,①同じ「チプ」(住居)に暮らす生活集団あるいは扶養関係と,②拡大的な父系親族の,二重の意味を担わされていた点である(cf. 金斗憲 1969(初版1949) 『韓国家族制度研究』)。解放後の家族研究史は,実際,この二重性の展開としても捉えうる。
1950年代以降に本格化する韓国農村社会を対象とした社会学・人類学的研究では,同じチプ(住居)に暮らし,基本的な生計を共にし,さらには生産・経済活動の基本単位ともなる近親者の集団を経験的に「家口」(世帯household)として再定義し,その境界を越えた近親間の依存・協力関係や父系親族の組織化と関連付けながら,その構成や役割・機能(社会構造的諸側面)について実地調査や統計調査に基づいた詳細な分析を行った。これに対し,産業化過程での農村社会の変化と都市的生活領域の形成に関する人類学・民族誌的研究や,植民地期にまで遡るオーラル・ヒストリーを主たる資料とする歴史民族誌的研究では,階級・階層やその他の社会経済的諸条件によって異なる様相を示す父系/非父系の近親者間の依存・協力関係と「家口」の編成を,集団/関係としての家族を一つの資源として活用する生計維持や社会上昇の戦略的・交渉的な諸実践として捉え直した。これは近代核家族理論への批判的視座を提起するものでもあった。このうちフェミニスト/ジェンダー人類学的な観点が強く表れる都市中産層の民族誌では,資本主義的労働市場で主たる「生計扶養者」となった夫・父親によって担われないあらゆる役割を引き受けるようになった妻・母親の交渉的実践と行為主体性,特に母性に注目が集まった。「専業主婦」として自己同定する彼女たちの役割は,家事・庶務,子供の養育と教育管理から,インフォーマルな経済・利殖活動と誇示的消費,さらには近親者との関係管理にまで及ぶ。
冒頭に述べた実践への制度/イデオロギーの複雑な介在という論点は,後者のような家族の再生産戦略に焦点を合わせた諸論考ですでに提示されていた。これを双方向的・相互作用的な過程に位置づけるにあたっては,多様な,時に競合する様々な「家族主義」の構築や,「家父長制」と総称される「家口」内部や近親者間の微視的な権力関係の再生産をめぐる議論が参考になるかもしれない。
近代家族を論ずる家族社会学・フェミニスト社会学や認知・行為モデルを論ずる文化人類学では,「家族」の実践に介在する社会規範,状況的合理性・実践的論理,あるいは国家・市場制度の原理を,しばしば「家族主義」(familism)という融通無碍な概念で対象化し,時に「家父長制」と関連付けて論ずる。例えば,農村社会の歴史民族誌で指摘されていたような,生活の必要性に促された依存・協力関係(実践的諸関係)といわゆる伝統的家族・親族理念(公式的親族)との齟齬や両者の折衝を通じた状況的合理性・実践的論理の構築は,「功利的・道具的家族主義」と「道徳的・理念的家族主義」との対立,ならびに「状況的家族主義」への止揚と捉えることができよう。産業化過程で形成された都市中産層夫婦家族をめぐる役割関係・性別分業や情緒性・親密性は,「儒教的家父長制」の「家父長制的資本制」への接合として論じられる(これを「新家族主義」と呼ぶ研究者もいる)。また,後期近代におけるリスク社会化と福祉レジームの再編成を論ずる近年の社会学では,社会の基本的な構成単位の「個人化」や個への志向性と人びとを強く拘束する諸々の「家族主義」との複雑な関係や,福祉制度の原理としての複数の「(制度的)家族主義」の可能性が論じられるようになっている。
このような「家族主義」・「家父長制」論からも垣間見えるように,現代韓国社会における概念装置としての「家族」の作用は,家族の現実とそれを論ずる社会科学的視角や啓蒙的言説,多様なメディアに媒介された表象,さらには法・政策論議が複雑かつ再帰的にもつれ合う状況をも呈しているのだと考えられる。このシンポジウムでは,家族をめぐる制度/イデオロギーの構築を腑分けしつつ,諸々の「家族主義」やその他の文化的レパートリーが家族の実践・交渉にどのように介在させられるのかを明らかにすることによって,韓国家族の現実へのより精緻な理解を試みたい。
最後に,概念装置としての「家族」の相対化に向けて,一つの手がかりを示しておこう。朝鮮・韓国社会における近代的な「家族」概念に含意されていた生活集団・扶養関係と父系血統の重なり合いとずれは,構造機能論では「家口」と家族・親族の相補性として読み替えられ,さらに農村社会の歴史民族誌的研究では実践的諸関係と公式的親族の弁証法的関係として分析し直された。この重なり合いとずれは,近年の韓国社会においても,血縁を主要な原理として制度化された近代家族ならびにそれを支える結婚制度と,制度的家族にとって過重な負荷となっているケア(養育・扶養など)の諸関係との齟齬(少子化・晩婚化・非婚・離婚などの形での顕在化)へと,位相を変えて再生産されているのではないか。なぜ制度的に規定された特定の近親者がケアの責任を担わなければならないのか。なぜパートナー間の分業や親密性,あるいは親子の扶養関係や情愛が,社会的/法的な結婚制度によって認証を受けなければならないのか。「家族」の当為性や自明性自体をも問い直すことで,一方でエミックな(当事者にとっての)/他方でエティックな(研究者にとっての)概念装置としての「家族」の脱家族的相対化を試みたい。
田中美彩都「近代朝鮮における家族「慣習」と「儒教的伝統」の形成過程―養子制度を中心に」
本報告では、近代(保護国期から植民地期)の朝鮮半島における、養子制度を中心に、韓国「儒教社会論」の下地としての家族「伝統」が形成される過程を明らかにしたい。統監府期に設置された法典調査局は1908~1910年にかけて、梅謙次郎の指揮のもとで家族をふくむ民事に関わる慣習をインタビュー・古文献により調査した。また1910年の民籍法施行に伴い、担当官署である警務局は各戸を網羅的に調査した。
法典調査局の調査結果は、植民地化後に『慣習調査報告書』(朝鮮総督府、1910・1912・1913年)として整理された。さらに1912年に制定された朝鮮民事令はその第11条で朝鮮人の親族・相続は「慣習」によることを定めた。以降は植民地政府が「慣習」と認めた内容が、朝鮮人の家族のありようを法的に規定することになる。
朝鮮の養子「慣習」は異姓不養、すなわち儒教祭祀を摂行可能な父系血統を同じくする同姓の男子のみに限ることとされた。しかし少なくとも統監府期の慣習調査時の資料や新聞記事などからは、多くの地域で、高麗時代以来の慣行である異姓を対象とした収養子も認められていたことがわかる。しかもその定義は、「食口」から祖先祭祀の摂行者に至るまで、地域や階層ごとに多様であった。
収養子は全人口の登録を最優先課題とした民籍に当初そのまま登録されたが、1916年、朝鮮総督府は「慣習」に則り収養子の民籍登録を禁止する。その結果、異姓養子縁組は法的な庇護を得られなくなった。異姓養子により家系を継承してきた宦官家や、民籍で養父子として登録された僧侶と上佐(弟子)の関係性も影響をこうむった。
なお、朝鮮総督府が異姓不養を「慣習」とみなした背景には、法典調査局の慣習調査に回答した儒学教養をもつ地域の指導層が調査者に理想とする家族像を強調したこと、『経国大典』『大明律直解』などの古文献調査の結果がこうした証言に信ぴょう性を与えた可能性を指摘しうる。一方女性の権利拡大を訴える朝鮮人知識人は儒教に基づく父系血統重視の家族制度の否定を「近代化」への道筋ととらえたが、1939年の朝鮮民事令改正による異姓養子の合法化から解放後韓国の民法典編纂に至る過程で、異姓不養を含む父系血統主義が「伝統」と名指されるようになったことも見逃せない。
つまり儒教化したとされる朝鮮後期以降の社会でも父系血統に基づかない多様な家族のありようが許容されていたが、統監府・朝鮮総督府が認定した「慣習」と韓国朝鮮社会が時代状況にあわせて求めてきた理想的な家族像が相互に作用しあうことで、儒教的な父系血統を重要視する「伝統」が生み出されたといえよう。
澤野美智子「韓国の家族における「模倣」と他者性」
家族の「理想像」は時代や場所によって異なるが、それぞれの形で存在し、人々は意識的・無意識的にそこから影響を受けていると考えられる。「理想像」のような家族を築こうとしたり、「理想像」を実現したいのにできなくて苦悩したり、逆に敢えて「理想像」とは異なる生き方を積極的に選択したりもする。
韓国の場合、儒教思想における家族規範、植民地時代や解放後の法制度における家族、西洋的な近代家族など、社会変化に伴って家族の様々な「理想像」が混在しつつ目まぐるしく変化してきた。1世代異なれば家族の「理想像」も異なるような状況下、西洋的な家族の〈模倣〉をしながら儒教的な家族の〈模倣〉も並行するというように、人々は複数の「理想像」の間で折り合いをつけ、あるいはそれらを組み合わせ、臨機応変に〈模倣〉を実践しながら家族を形成してきた。
しかしそれらは必ずしも常に調和していたわけではない。人々は複数の「理想像」の間で苦悩を抱えることもある。発表者が韓国で聞き取りを行なってきた乳がん患者たちの語りにおいても、病気に罹った原因として語られる家族の問題には、そのような複数の「理想像」の狭間で苦悩する女性たちの姿が浮かび上がる。それは時には自分が理想とする家族と、自分の親世代が理想とする家族、あるいは自分の子世代が理想とする家族との間の狭間である。また時には、自分が実現したい家族の「理想像」と、その実現を阻んだり家族規範を逸脱したりする家族成員との間の狭間である。
一方で現代韓国社会においては、家族の様々な「理想像」が根強く存在しつつも、家族形態の〈模倣〉に執着するより合理性を優先することが珍しくなくなっている。例えば急速に進行する少子化に見られるように、家族の「理想像」を〈模倣〉しなくていい自由と、自らの意志と責任でライフスタイルを作り上げていかねばならない試行錯誤の時代を、人々は生きていると言えよう。
株本千鶴「ケアの社会化と家族主義─韓国における介護・看病のばあい」
本報告は、韓国におけるケア提供システムと家族主義の関係について考察するものである。ケアのなかでも介護(主に高齢者対象)と看病をとりあげ、それらを対象とした制度・政策および実践と家族主義の関係、そして、それらが目的とする介護・看病の社会化の現状について検討したい。
韓国の社会福祉や社会保障、社会政策を対象とした研究では、ケア提供システムが家族主義から強い影響をうけていることが明らかにされている。ここで用いる家族主義は、社会学者の金東椿が家族主義の類型のひとつとしてあげている「制度的家族主義」とほぼ同義である。「制度的家族主義」とは、「保育、高齢者介護、福祉などを国家や社会が担当するよりも家族が優先的に担当すべきであるとする思考や、そのような思考や慣行から作られた福祉、介護などの家族依存的な法・制度」をさす。
制度的家族主義は、現実の家族介護および看病の担当者に過重な負担を強いている。その負担を軽減するために支援策が実施されているが、成果はあまりあがっていない。
たとえば老人長期療養保険制度は、その目的のひとつを「家族負担の軽減」、すなわち介護の「脱家族化」としている。しかし、インフラ不足改善のために作られた「家族療養給付」は、介護の「家族化」を促す要素となっている。「家族療養給付」は、資格をもつ療養保護士が利用者である家族を介護した場合に介護報酬を給付するものであるが、訪問療養受給者の約20%が家族である療養保護士から介護をうけている(2020年1月)。家族療養保護士による介護には長所もあるが、不正受給やケアの点検・管理の困難という短所もある。看病にかんしても、たとえば、看病人(付添い)の雇用が患者家族の重い負担になっているが、これに対する支援策も看病の「脱家族化」を顕著に進展させるほどの成果をあげていない。
報告では、上記のような介護と看病を対象とした制度・政策および実践と家族主義の関係、そして、介護と看病の社会化の現状について検討したのち、ケアの社会化の今後についても考えてみたい。ケアに関する問題が以前よりも重視される現代韓国社会では、ケアに関する社会的権利、あるいは、ケアの社会的保障の確立をめざす研究や活動が活発化している。一方で、ケアの家族化を維持・強化する、ケアサービスの産業化や孝行奨励・支援制度の実施などがある。これらの社会的事実によって「制度的家族主義」がどの程度変容するかが、ケアの社会化の今後のあり方に関わってくるであろう。
以上
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内