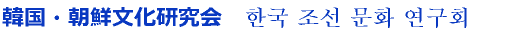![]()
第91回研究例会
運営委員会での検討の結果、対面とWeb会議サービスのZoom上でのハイブリッドにて開催しました。
記
日時:2025年2月8日(土曜日)15時~18時
開催方法:東京大学(本郷キャンパス) 赤門総合研究棟7階738号室+Zoomミーティング
発表者①:野辺陽子(日本女子大学人間社会学部現代社会学科准教授) 題目:児童福祉としての養子縁組の日韓比較——グローバル化のなかの「家族主義」の理解へ向けて 本発表の目的は、日韓の児童福祉を目的とした養子縁組の展開から、グローバル(という名の「西欧」の規範)とローカルな規範や制度がいかに交渉されるのかを分析することを通じて、「家族主義」とひとくくりにされる日韓の共通点と相違点と、その社会的背景を考察することにある。 子どもの権利条約というグローバルな規範は、総括所見などを通じて、各国の子どもに関連する制度に圧力を加えている。制度に求められる改革は、親のあり方や子どもが育つ場にも影響を及ぼすが、必ずしも各国が同じような状態に収斂するわけでもない。 本発表では、特に2000年代以降の日韓の児童福祉としての養子縁組を主たる対象に、それと関連する制度として、生殖技術(第三者が関わる生殖技術を含む)、家庭委託(里親養育)、人工妊娠中絶、施設保護、保護出産なども取り上げ、法律、政策、運用、実態等を検証する。養子縁組以外の制度も検討する理由は、これらの制度の動向が、養子縁組の需要(子どもを引き取りたいというニーズ)と供給(子どもを養子に出したいというニーズ)に影響を与えているからである。 養子縁組の動態と関連する制度、その社会的背景の分析から、「家族主義」と呼ばれるものを、グローバルとローカルが交渉するなかで組み替えられる国家—家族—個人の配置や、子どもの保護、女性の保護、男性の責任という観点に分解して考察することで、日韓の「家族主義」の理解を深化させたい。
発表者②:田村あすか(東京都立大学人文科学研究科博士後期課程) 題目:交錯する二極——韓国における代案教育と公教育の接近およびその展望 韓国社会では、1990年代にオルタナティブ教育(以下、現地語に倣い「代案教育」と呼ぶ)が活発化し、競争的で画一的な公教育に代わる新たな教育のあり方が模索されるようになった。先行研究が示すように、従来は「代案学校/一般学校」、あるいは「代案学校/韓国社会」という二項対立的な認識が議論の前提とされてきた。特に代案学校の生徒が後者を「主流」と形容し、代案教育の価値観とは相容れない世界だと捉えられている様相は多数記述されている。しかしながら近年、韓国の公教育や大学入試制度は、試験の点数に現れない多様な要素を評価する方向に変容しており、その流れで従来代案教育の側にあった手法や実践が採用されつつある。すなわち、代案教育と「主流」の関係は複雑化し、二項対立的な図式はもはや適用不可能になっていると言える。しかし、両者が接近する一方で、評価方法における相反する要素が新たな緊張関係を生んでもいる。具体的には、「主流」の観点からは代案教育の評価体系が公平性や透明性に欠けるとされ、代案教育側はその自由さが損なわれる懸念を抱えている。こうした状況を踏まえ、本発表では非認可代案学校「堤川ガンジー学校」の事例を取り上げ、「主流」の価値観から独立した教育実践が示す意義を明らかにする。これを通じて、上記の緊張関係が韓国社会における教育と価値観の変容にどのような示唆を与えるか考察する。
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内