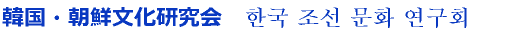![]()
第92回研究例会
運営委員会での検討の結果、対面とWeb会議サービスのZoom上でのハイブリッドにて開催しました。
記
日時:2025年4月5日(土曜日)15時~18時
開催方法:東京大学(本郷キャンパス) 赤門総合研究棟7階738号室+Zoomミーティング
発表者①:鄭憲穆(韓国学中央研究院人類学専攻部教授) 題目:社会的経済とマンション団地の結合——協同組合型公共支援民間賃貸住宅の登場と意味 現代韓国社会でアパート(マンション)は「マイホーム購入」の夢が込められた代表的な住居様式であり、最も一般的な財産増殖モデルとして位置づけられてきました。 本研究は韓国社会で最も資本主義的な住居空間に該当するマンション団地と、冷酷な資本主義システムの代案を標榜する社会的経済の結合を試みた新しい実験に注目します。 その対象は「ウィステイ(WeStay)」という名前の「協同組合型公共支援民間賃貸住宅」です。 韓国ではマンション団地は商品としての特性が強く表れる住居空間で、公共性や共同体とは程遠いものとみなされます。 反面、初めからマンション型コミュニティーを標榜したウィステイは入居予定者全員を協同組合構成員として募集し、正式入居以前から「共同体造成」のための活動を活発に展開しました。 本発表は、ウィステイという実験的住居モデルの特性と社会文化的含意に関する研究です。 まず、ウィステイの登場背景と主な特徴を検討し、「協同組合型公共支援民間賃貸住宅」という事業モデルの性格を考察します。 続いてウィステイ団地で入居初期に発生した葛藤の展開様相と原因を「空間の社会-物質的構成」という観点で分析し、これによって発生した「共同体の危機」が共同体の再呼び出しと積極的な実践活動を通じて解消される過程を見てみます。 これを通じてウィステイモデルが2020年代の韓国社会で持つ社会的意味を考察し、今後の課題を議論します。
発表者②:小谷稔(東京大学(学振PD)/全北大学校客員研究員) 題目:植民地朝鮮における農業学校の設立状況と入学生出身地域分析—全州・井邑・裡里農業(林)学校を中心に— 本報告の目的は、植民地朝鮮の全羅北道に農業(林)学校が設立されていく過程を明らかにするとともに、農業(林)学校に入学する朝鮮人青少年男子の地域移動の実態を、当時の学籍簿史料を通して分析することである。近年、実業(農業)学校の研究や、学籍簿を用いたそれも進みつつあるが、本報告は道レベルで、3つの学校を総合して分析した点に特徴がある。 農業学校は、普通学校を修了した農業者の子弟を主たる対象とした、中等程度の実業学校の一種である。初等教育の充実と終結教育化を唱えながらその就学率すら過半を越えなかった植民地朝鮮において、さらに上級の学校に通うことのできた学生たちはまさに植民地エリートであり、とくに農村部におけるそれは、いわゆる「農村エリート」であった。 そのような農業学校が地域に設立される過程や、運営されていく状況を明らかにすることは、植民地農業政策の中にあって教育の受け手である学生や農業学校が設置された地域の有志たちが学校や新式教育をいかに捉え、行動したのかを明らかにできる点で意義を持つと考えられる。また学生である青少年たちが郡境を、さらには道境を越えてこれらの学校に入学してくる様子を明らかにすることは、当時の青少年たちによる教育機会獲得を理由とした地域移動が道単位で動態的に解明されるという点でも意義があるだろう。 具体的に本報告では、まず学校史や地域教育史、新聞史料、統計資料などを用いて、全羅北道に農業学校が設置・拡充されていく過程や各学校の教育の類似点・相違点などを明らかにしていく。続いて報告者が2022年度に国家記録院に公開申請して入手した全羅北道の全州・井邑・裡里農業・農林学校の3つの学籍簿に収録されている、2,200人余りの学生の出身地データを整理・分析することで、学生の移動の動態的把握を試みる。
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内