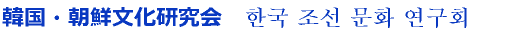![]()
下記の通り、第26回研究大会を対面とオンラインの併用にて開催いたしました。
日時:2025年10月25日(土) 10:00〜18:00
場所:東京大学本郷キャンパス 国際学術総合研究棟1F 三番大教室
□ プログラム
10:00〜12:00 一般研究発表
新里喜宣 「「崔順実ゲート」と「第20代大統領選挙」における巫俗言説」
大沼巧 「朝鮮半島の海面における伝統的な権利・権益の特徴と日本統治後の変化について」
羅孟晋 「迂回としての「チプ」—グリーンハウスにおける家族と世帯の改編」
12:30〜13:00 会員総会
13:10〜18:00 シンポジウム「今また振り返るフィールド」
趣旨説明:林史樹
報告:平木實 「浅学児の韓国体験」
鶴園裕 「韓国留学時代—1970年代を中心に」
伊藤亜人 「フィールドワークと社会変化」
嶋陸奥彦 「予測と不測」
吉田光男 「現場を歩いた歴史学」
コメント:権香淑
鈴木文子
総合討論
18:30〜 懇親会 和食ごはんと酒 縁 本郷三丁目店
東京都文京区本郷7-2-12 スカラグリジアB1
電話050-5488-7558
□発表・報告要旨
(1)一般研究発表の要旨
新里喜宣 「「崔順実ゲート」と「第20代大統領選挙」における巫俗言説」
1945年の解放以降、巫俗は迷信として批判されながらも、同時に韓国文化の源泉として再評価の対象ともされてきた。たとえば、1970年代のセマウル運動においては大々的な迷信打破運動の一環として、全国で巫俗の儀礼の場所であるクッ堂が破壊されたが、一方で政府は民俗政策を推し進め、多くの巫俗儀礼が無形文化財に登録されるに至った。このような流れのもと、巫俗を肯定的に捉える視点が韓国社会でひろく共有されることとなる。報告者の見るところ、1980年代の社会浄化事業を最後に、巫俗を否定的に捉え、クッ堂の破壊にまで事が及ぶことはなくなった。以後、新聞や雑誌等のメディアに単発的に巫俗を否定的に捉える連載記事が掲載されることはあったが、巫俗に対して公的な批判が持続的に加えられることはなかったと考えられる。
しかし、2010年代後半より、突如として巫俗がメディアで露骨に批判され始める。2016年の「崔順実ゲート」がその発端である。当時の現職大統領・朴槿恵(敬称略、以下同様)を裏から操り、国政を壟断したと評価される核心人物として崔順実(本名:崔ソウォン)の存在が明るみに出たのである。これに怒った民衆のデモに触発され、2016年12月9日には国会で大統領弾劾訴追案が可決、2017年3月10日には憲法裁判所によって大統領の罷免が宣告された。この一連の事態・事件は崔順実ゲートと呼ばれるが、崔順実ゲートにおいて特に取り上げられたキーワードは「巫俗」であった。崔順実の父・崔太敏が小さな教団の指導者を名乗っていたこと、朴槿恵の様々な発言が巫俗的と捉えられたことにより、多様な角度から巫俗批判が提起された。
崔順実ゲートでは大統領弾劾にまで至ったが、その後巫俗批判は多少の小康状態に入る。そして、2021年から本格化する第20代大統領選挙において、再び巫俗は激しい攻撃にさらされることとなる。国民の力の候補選出における討論会で、2021年10月2日、尹錫悦候補の手のひらに「王」の字が書かれていたことが判明し、これが巫俗ではないか、との疑惑を呼び起こし、激しい巫俗批判の発端となった。以後、2022年3月9日の大統領選挙まで(そして2025年の現時点まで)、巫俗は常にメディアで否定的に扱われてきた。
本報告は、崔順実ゲートと第20代大統領選挙における巫俗言説を、巫俗言説の歴史的展開のもと捉えようとする試みである。これら二つの出来事において巫俗は、政治を裏から操る韓国社会の闇、なにか得体のしれない存在として言及された。しかしその一方で、じつに多くの媒体、主体が巫俗について語りつつも、前述したセマウル運動や社会浄化事業ほど踏み込んだ巫俗批判がなされなかったことも事実である。その意味を、とりわけ1960年代以降社会的に共有されることになる、巫俗を再評価する動きとの関連で捉えてみたい。
大沼巧 「朝鮮半島の海面における伝統的な権利・権益の特徴と日本統治後の変化について」
本報告は、近代移行期の朝鮮半島の海面における権利・権益の実態とその変遷について、地域の実態に沿って明らかにしたものである。これまでの韓国漁業史研究においては、日本人漁民の進出や日本人による漁場侵奪という観点から進められることが多く、韓国の海面が単なる侵奪対象とみられる傾向にあった。こうした研究は、日本統治期以来の朝鮮漁業に対する停滞的な見方や日本人による「開発」といった視点に対する批判的な視覚の必要性を考えれば、戦後の朝鮮史研究としては自然な流れだったといえよう。
しかし、実際には朝鮮時代以来、海面には明確な根拠のあるものから慣習的なものまでさまざまな権利・権益がすでに存在しており、それは日本が無視できるようなものではなかった。そのため、日本の朝鮮半島海面への進出とそれによって起こりうる朝鮮社会の変化は一様ではなく、具体的な事例を見ていく中で、その特徴を明らかにしていかなければならない。
本報告では、海面の権利・権益の全体像を意識しつつも、主に2つの事例に焦点を当てることにした。一つは、朝鮮時代以来漁業が盛んであった慶尚南道の事例である。同地域では、王室のかかわりや大韓帝国期の混乱、その後の日本の実業家の関与など、時代の変化に大きな影響を受けたという点で、海面の権利・権益の変化を考えるうえで示唆するところが大きい。もう一つは、朝鮮時代前期から塩業が盛んだった忠清道の事例である。同地域の塩業は、朝鮮時代に国家財政としての機能を期待されることもあったが、次第にその機能を失っていった。それでも、その後も王室の関与や地元民の努力により、少なからぬ利益を生み出すことがあったことも確認できる。ただし、塩業における権利・権益は、それほど重要なものとはみなされず、日本統治期には伝統的な権利・権益の存在を確認することは困難になっていた。
本報告では、こうした具体的な事例を紹介するとともに、現在までの研究の課題や今後の方向性についても示していきたい。
羅孟晋 「迂回としての「チプ」—グリーンハウスにおける家族と世帯の改編」
近年の韓国家族研究は、「脱家族主義」に焦点を当て、近代的概念装置としての「家族」の自明性に疑義を呈し、その構築過程と揺らぎを捉えてきた。本発表では、こうした議論を踏まえ、都市住民による農村への移住と就農(帰農)に着目し、生活と経営にまたがる多重的関係性を包摂する「チプ」の可塑性を再考することで、ポスト産業社会における家族・世帯実践の「迂回的」な性格を示唆する。ここでいう「迂回」とは、ジレンマに直面しても既存の環境や規範に正面から対抗せず、それらの両義的な複数の含意のあいだを行き来しながら、実践的判断によって条件や規範性を変容させていくダイナミクスを指す。
2010年代以降の帰農は、国家・地方行政による支援のもと、資本・技術の投入や外国人労働者の流入と交錯しつつ、小農生産を基盤とする農業自由化の枠組みに統合されていった。一方、「IMF危機」以降の中産層的核家族の一部は、自己搾取的家族労働と柔軟な生産様式(自営業や農業等)を接合することで、小規模家族経営体として再編されてきた。このような二重の転換のなか、帰農者と労働者が交差する農家世帯では、「家族」という関係性を媒介とするケアの倫理と権力関係が両義的に動員され、不安定な「チプ」が編成されている。
本発表でとりあげるイチゴ栽培は、小規模かつ高収益の経営形態として帰農者に選好されるが、温室施設内での不法居住や長時間労働が特徴でもある。こうした営農環境のもとでは、帰農をめぐる夫婦の交渉と核家族の再編が重要な論点となる。都市生活に挫折した夫による帰農の提案をめぐり、妻は都市残留か農村移住か、家事専従か農業への参与かの選択を迫られ、議論の末、世帯構成は夫の単身就農・温室居住、夫婦移住・温室居住、あるいは親子移住・市街地居住へと分岐する。一部では、子育てを終え農業教育を受けた妻が、農場経営に参入し夫の権威を相対化する試みも見られる。ここでは家族へのケアがそれぞれの行動の善き動機として語られる一方で、夫婦間の権力関係や願望には微細な変動が露呈している。
くわえて、共同労働や隣接居住を通じた外国人労働者との擬似的な親密性も際立つ。帰農者は彼ら彼女らを自己搾取的家族労働に取り込み、「情」や日常的な配慮を通じて農場への帰属意識を醸成しようとする。時には親しいコミュニケーションも行われるが、より良い条件を求めて夜逃げする労働者も少なくない。帰農者は、自らの家族のために働く労働者に同情を寄せる一方、「情」への裏切りを道徳的に非難し、一定の境界を保った相互依存的な関係性を模索している。
このように移動性と不確実性が高まる現代農業において、帰農者たちは、実践と規範を一義的に受け入れるのではなく、それらが孕む両義性のあいだを「迂回」しながら、「チプ」のあり方を再構成している。本発表は、こうした実践の動態に注目し、現代韓国家族研究に対して一つの解釈枠を提示したい。
□ (2)シンポジウム「今また振り返るフィールド」
韓国・朝鮮文化研究会は2000年10月に設立された。第1回研究大会シンポジウムは「交叉するフィールド」と題して開催され、続く第2回研究大会シンポジウムも「韓国におけるフィールドのあり方」と題されたように、設立当初から「フィールド」という用語で緩やかに捉えられるような実証的・経験的な調査研究の場が意識されてきた。しかし、その後、四半世紀が過ぎ、フィールドとして捉えられてきた研究者それぞれの研究の場も、また研究会を取り巻く環境も様変わりした。そこで今大会ではこのような変化にともなう研究対象や方法の変化を振り返ってみたい。
ただ、フィールド概念は、研究会内で必ずしも一致しているとは言い切れない。さしあたり、設立趣旨文には「現場を重視する研究」とあり、そこから考えると、フィールドとは、一義的に「現場」(たとえば各自の研究を構成するものが実際に生起する場)と置きかえられる。また特定の地域・地点や場所に焦点を合わせて「現地」という語で捉えることもできる。もちろん、フィールドとの距離の取り方やアプローチの仕方は研究分野によって異なってくるほか、朝鮮半島が南北に分断され、政治体制にも違いがあるため、フィールドの枠組みや意味するところも一定ではない。たとえば、従来の美学や音楽学、文学研究において、作品の鑑賞や読解の範囲であれば、研究者同士の交流や作品の原物に触れる以外の目的で、現場(現地)に足を運ぶ必要を感じないこともありえたかもしれない。また体制が異なる国家に分断された状況で、現場(現地)に足を運ぶこと自体が政治的メッセージと捉えられることもあり、歴史学などでは渡韓して研究すること自体が、慎重にならざるをえない時期もあった。
一方、フィールドを研究者とその研究者が調査・研究の過程で遭遇する他者や場所とのインタラクションを通じて生成される場と捉えれば、研究分野を問わず、研究者は日々の研究活動を通じて絶えずフィールドを生成し、更新しているともいる。すなわちフィールドは、その時々のインタラクションに応じて生成・変容する可変的な空間とも捉えられ、その意味ではすべての研究者が何らかのフィールドに身を置いていることになる。これを相互に対照することを通じて、それぞれの研究実践への省察を深めることが可能となろう。また本研究会会員の多くが現地の言語を駆使して研究を進めていることを考えれば、それぞれのフィールドを構成する現地・現場経験の重なり合いも決して小さくはないといえる。とくに現地調査を重視する民俗学や宗教学、社会学や人類学などの分野では、日韓国交正常化以降、比較的に早い時期から研究者が現地に足を運び始めたが、それだけに早くからフィールドの変化に対応が迫られてきたし、その対応から得られる視点は、研究分野を越えて広く共有できるものとなるだろう。
今大会では、初期に議論したフィールドに再び焦点をあてるが、絶えず変化をしてきた研究のかたちは、研究者がフィールドと向き合い始めた初期からどのような違いをみせてきたのか。少し遡るだけでも光州事件、ソウルオリンピック、アジア通貨危機、サッカー日韓W杯、韓流ブームといった出来事は、韓国社会に多大な影響を与えた。登壇者は研究歴の長い歴史学者と人類学者になるが、これまでフィールドで経験した変化を、その時々でどう受け止め、その変化にどう対処したのか。受け止め方や対処法は個人によっても研究分野によっても異なるが、この間のフィールドの変化とそれぞれが身を置く研究分野の研究環境や研究傾向の変化について多角的に振り返っていただく。
当会が標榜してきた「現場を重視する研究」の25年の歩みを、戦後日本の韓国・朝鮮研究の流れの中で捉え直し、韓国・朝鮮研究のフィールドをみつめ直す。さまざまな変化をどう捉え、対処し、研究を続けてきたのか、全体討論では学問分野の垣根を越え、登壇者の経験や知恵、模索を聞き、共有することで韓国・朝鮮研究のさらなる発展につなげたい。
報告題目
報告:
平木實 「浅学児の韓国体験」
私は1964年3月に留学したが、過去に日本の植民地支配を受けた当時の韓国では、日本に対する国民感情が非常に厳しく、ソウルでは日韓会談反対の集会や学生デモ、戒厳令を目の当たりにした。それをみて日本人としての責任が非常に重いという認識をもった。そうした体験は日本にいて報道で見聞するだけでは理解できない状況であったと考える。個人的には、朝鮮学科という当時の日本で唯一の学科を卒業したこと、中山正善・高橋亨教授を中心にして結成された朝鮮学会が組織されていて、その国際交流によって、韓国の大学関係者の好意を受けることができたように思う。また一般の人々も韓国文化を学びに来ているということで好意的に接してくださる人が多かった。韓国というフィールドで体験した様々な事象のなかで、つぎの二点に絞って報告したいと思う。
1.所謂倭色宗教の扱われ方について
当時の韓国社会では、倭色文化を排撃する必要があるとして、言語や歌謡界、映画界などの日本文化をはじめ、創価学会や天理教などの宗教団体がキリスト教、仏教などのような国際的な宗教でないとして強い行政指導を受けていた。天理教については、天理教の信奉する親神の神名のなかに、伊弉諾尊、伊邪那美尊などの天照大神の親にあたる神名を用いているとして不敬罪として教義の公開を許されず、明治時代の日本政府の宗教政策により弾圧を受けたりしていたが、韓国では、逆に韓国を植民地支配した日本の天皇の皇祖神を信奉している宗教団体であると批判されたり、創価学会は「韓国人の信徒も「南無妙法蓮華経」となにはばかることなく、日本語で念仏を唱えている創価学会は、日本仏教の一分派である日蓮宗を信じる信徒たちである。…日蓮が北条軍事政権の御用宗教家であったのと同様に日蓮宗は、東條軍事政権の忠実な御用宗教であったのである。といった理由で批判を受けていた。…」(「京郷新聞」1965年8月5日号)
2.ソウル大学校大学院史学科国史学専攻というフィールドにおける体験
ソウル大学校の大学院史学科国史学専攻碩学士課程に外国人学生として入学することが認められた。ソウル大学校のキャンパスは、東崇洞にあった旧京城帝国大学の校舎がそのまま使用されていた。研究を続けたい卒業生たちは、高等学校の教員などをしながら、ソウル大学校奎章閣の閲覧室に通い、小瓶に入れたキムチと麦飯弁当持参で貴重な文献資料に取り組んで研究にいそしんでいた。学生デモなどは無視して政治に関与せず学問に打ち込んでいた。韓国の若手研究者が熱心に研究に打ち込む姿に刺激を受けて、とくに才能があるわけでもない自分はもっとしっかり研究しないといけないと痛感した。当時のソウル大学校の若い歴史研究者たちは「なぜ韓国は日本の植民地支配を受けるようなことになったのか」という点について強い関心を抱き、それを究明するためには朝鮮時代後期の研究を推進する必要があり、社会経済史の研究、農業史の研究、「実学派」学者たちの研究を深めていく必要があるという傾向が強かったように思う。
鶴園裕 「韓国留学時代、1970年代を中心に」
1950年生まれの私が、韓国に留学したのは1974年から78年で、韓国は朴正熙(1917~79)軍事政権の末期であった。1972年には南北共同宣言(7月4日)が発表され、一方では10月維新を行って、軍事独裁体制が強化され、1973年には金大中拉致事件、74年春には民青学連事件が発生して、早川・立川の二人の日本人が逮捕され、韓国の刑務所に収監されていた。同年8月15日の光復節に日本が支援したソウル地下鉄が開業した同じ日に、在日コリアンの文世光による朴正熙狙撃事件が発生し、陸英修大統領夫人が死去した。
このような時代を背景に、私は1974年4月に観光VISAで韓国に入国し、韓国の延世大学校の韓国語学堂で韓国語の勉強をしていた。当時は観光ビザで入国しても3か月の短期留学ビザに切り替えが可能であると言われていたからである。しかし、前述のような時代背景の為に再度正式な留学生ビザの取得が必要であるとされ、日本への一時帰国が必要であると言われた。VISAの相互主義という理由であった。2か月程度で許可がおりるであろうと言われたが、正式な留学生資格のVISAが下りたのは文世光事件後の8月31日であった。
半ばあきらめかけていた韓国留学を再開したのは9月11日からであり、その後も6級までの韓国語学堂の正式のコースを終えて、75年秋には延世大学校の文科大学院、韓国史学科の碩士過程(日本の修士課程に当たる)に入学する事になる。
その後の3年間の金容燮教授の指導による大学院の学生生活は、楽しくも厳しいものであったが、今回のレジュメでは字数の制限もあるので、朝鮮史という歴史学と文化人類学という事のフィールドの共通性と違いという様な事を意識しながら、シンポジウムでは報告したいと思う。時間があれば、地下鉄における席を譲る作法の消失や、保身湯(ポシンタン、犬肉食)とクジラ肉食ではどちらが伝統食として生き残るか、葬礼における土葬から火葬への変遷の問題なども歴史学や文化人類学の立場から論じてみたい。
(参考文献)
鶴園裕、1995「朝鮮史研究と文化人類学」『金沢大学教養部論集・人文科学編32』
原武史、2025「9年ぶりのソウル地下鉄」『歴史のダイヤグラム』朝日新聞7月5日(土) be on Saturday
原武史、1996『直訴と王権、朝鮮・日本の一君万民思想史』朝日新聞社
平木實、2019「朝鮮学と私」『朝鮮学報』251
油谷幸利、2025「私と朝鮮学—油谷幸利先生に聞く—」『朝鮮学報』265
カーター・J・エッカート(松谷基和訳)、2024『韓国軍事主義の起源 青年朴正熙と日本陸軍』慶應義塾大学出版会
伊藤亜人 「フィールドワークと社会変化」
韓国・朝鮮社会を研究対象とする研究者の間でも、現地社会あるいは人々との関わりのあり方は様々である。現地研究の中でも人類学が提唱してきたフィールドワークは、研究者が自ら現地社会に身を置き、自身の観察と洞察に基づき記述をするもので、事例研究を通して人間社会の一般化に寄与するという展望に立っていた。研究者も対象も個別であって、両者の関係も個性や相性に大きく依存するものだった。私自身が1965年に進学した東京大学の文化人類学教室は、学科設置の段階から米国の影響のもとで、泉靖一教授の積極的な発信によって「人間の総体的研究」という理念を掲げて、とりわけフィールドワークという新鮮な手法が注目を惹いた。
本企画は、フィールド社会の変化に注目して、研究者の側の経験と展望を共有することが趣旨と理解している。人類学ではかつては主として未開社会を対象とした共時的な研究姿勢が重視され、通時的な観察記述とか動態的研究が提唱されてはいても社会変化研究が主流とはなりえなかった。歴史は背景として記され、記憶や記録や遺物などを通して社会変化を記述するに留まっていた。今日では、人類学自身が近現代の社会変化の中で立ち位置を自覚するようになったが、もともと社会は常に変化するものであり、研究者の社会性も認識も変わり、両者は相互性のもとで生成するものである。また研究と開発(介入と変化)を一体化させて積極的に社会変化に関与する試み(Research and Development, Participatory Development)は開発研究の主流をなしてきた。
以下に自分の経験をもとに、共有できると思われる点を思いつくまま挙げておく。
・文化人類学におけるフィールドワークの位置づけ。人類学の研究者として必須かつ通過儀礼といえる位置づけ。異文化に身を置いておこなう全人格的かつ知的な試みであり、人文社会学の中でも斬新かつ魅力的な経験として評価。
・未開社会を想定した静態的なフィールド像。個人が直接観察・記述できる小さくてシンプルな社会単位に対象を設定。総体的(holistic)な観察・記述を意識。
・農民社会や町社会などの複雑社会complex societyにもフィールドワークの手法が試みられたが、日本では大幅に遅れていた。
・東アジア文明圏に対しては大伝統の文献資料と専門性の壁 (歴史、思想、宗教)を避ける傾向。帝国主義との関連を忌避する消極性。日本研究を研究対象とする展望も遅れた。
・日本の漁村・家船の調査(1966~1969):差別に起因する困難。藩政時代の特権と御役、漁村社会の変動・流動性と社会経済史的研究への関心。
・五島福江の農村での体験(1969~1971):経済と行政、技術導入、開発をめぐる農村社会の課題への関心。Anthropology of Development。
・珍島農村での現地調査(1972~)。総体的な研究理念と長期的展望。静態的な印象と植民地期〜地方振興、開発独裁国民化(セマウル運動・国民経済)に伴う社会変動。物質文化・生態学的・経済的な変化。眼前の農村生活の記述を優先し、歴史については手遅れ。
・人口流動、過疎化と老齢化、機械化と労働慣行の変容。チプの形骸化、門中の再編、祭祀と墓地、農村の教育、多文化家庭、外国人労働者、老人と貧困、地域消滅の危機、珍島学会、異邦人・研究者の経験。
嶋陸奥彦 「予測と不測」
私が初めて韓国で現地調査を行ったのは1974年8月から一年間、全羅南道羅州郡の農村で、家族・親族組織、村落組織、農業活動などを中心とするものだった。
二度目の調査は1980年と81年の夏に慶尚北道星州郡の農村で、全羅南道との地域差を確認しようという目的だったが、この時に一つの親族組織の族譜をゆっくり見せてもらうことになった。注目したのは、歴史のなかで一族の人々が全国各地に移住して居住するようになっているという実態であった。
国立中央図書館でその一族の族譜をコピーし、それによって一族の人々の現住地を確認することができた。それをもとに、82年の夏に全羅北道、忠清南北道、慶尚北道の村々を訪問したが、この調査を通じて、編纂時期のことなる五つの族譜を入手することになった。
これらの族譜を比較すると、時代が下るにつれて系譜が長くなるだけでなく、版によって新しく記録されるようになる分派がある一方で、記録されなくなる分派もあることが分かった。そこから見えてきたのは族譜編纂に関与した全国各地の子孫たちの関与の歴史だった。これを契機に私自身の関心も親族組織の歴史過程へと広がることになった。
1986年秋から一年間、ハーバード大学で研究する機会を得た。そのとき出会ったのが朝鮮時代の大丘戸籍である。その分析を通して、17世紀末から19世紀中期にわたって形成されてゆくいくつかの親族集団の存在を確認した。
1996年から98年にかけて、これらの親族組織の現状を確認するための現地調査を行った。そのとき目撃したのが、大邱市街の拡大に巻き込まれた親族集団の対応であった。特に目をひかれたのが市街地にとりこまれた墓地の移転問題だった。
大邱市での都市化現象の調査をしていた時に、以前に星州郡での調査のときに世話になった門中の宗家の主人と偶然にも再会することになった。そこで知ったのは、農村の宗家の奥さんが大邱市街地の露天商街で露天商をしているということだった。
これをきっかけに、2000年から2003年にかけて、大邱市達西区の露天商街の調査をすることになった。これが私にとっての最後の本格的現地調査ということになった。
自分の研究史を振り返ると、それは予測もしなかった事態との出会いの繰り返しであった。
吉田光男 「現場を歩いた歴史学」
「交差するフィールド」という本研究会の趣旨に立ち返って、1970年代以降の、朝鮮近世史研究という専門分野(フィールド)と、朝鮮半島という事象生起空間(フィールド)の二つのフィールドで、どのような活動を行ってきたのか振り返ってみる。
私がその中に身を置いてきた1970年代以降の、日本における朝鮮近世史研究の動きは、おおよそ以下のように概観できる。
①1970年代(黎明期)。文献資料による研究のみだったが、ようやく韓国現地に目が向けられるようになる。少数の先達が韓国に入り始めた。朝鮮近世史研究者の現地入りが遅くなったのは、朝鮮近世史に対する関心が薄く、そもそも研究者自体が僅少であったからである。近世史研究はほとんど田川孝三氏(『李朝貢納制の研究』、東洋文庫、1964年)という孤塁によって細々と行われている状態であった。朝鮮史に対する研究的関心は、古代史と近代史、それも日本との関係に集中しており、近世史は大学でもほとんど教育が行われていなかった。
②1980年代(助走期)。ようやく近世史(李朝史)の研究者が育ち始め、1981年10月に朝鮮史研究会大会で「李朝史の諸問題」をテーマにしたシンポジウム開催にこぎ着けたが、内容はさておいて「初めて近世史シンポジウムができたこと」が評価される状態であった。
一方で、少数の研究者による現地回りが始まる。吉田の場合、この時期に、嶺南、湖南を中心にしてマウルタニギを繰り返した。安東川前里義城金氏、安東西後面鶴峯宗家、奉化酉谷里安東権氏、礼安下渓里李退渓故家、海南尹氏(尹善道宗家)など、宗家と集姓村を回る。一方ソウルでは、17〜19世紀の古地図と地籍図などによる街路調査、戸籍台帳による街区調査を継続する(『近世ソウル年社会研究』、草風館、2009年)。その多くは、再開発計画によって21世紀になって湮滅してしまった。
③1990年代(号砲)。吉田が全国の若手研究者や大学院生を連れて、意識的な「現場回り」を行う。各道の近世史関係「現場」(集姓村、宗家、書院など)をひたすら回り、住民の聞き取りを行う。目的は、現地感と現場感の養成、人々とのつきあい方の訓練、そして何よりも、近世の残り香を「経験」すること。この時に訪問した集姓村や宗家の多くがその後急速に変容し、オルシンの別世、過疎化、集落の観光地化などで「近世の残り香」が失われてしまった。
本シンポジウムでは、このような1970年代から現在までの朝鮮近世史研究が、「現場」とどのように取り組んできたのかについて、自分の「経験」を中心にして話題を提供し、「経験」の意味を議論したい。
韓国・朝鮮文化研究会第26回研究大会委員会
委員長 仲川裕里
委員長 仲川裕里
記
韓国・朝鮮文化研究会第26回研究大会
韓国・朝鮮文化研究会第26回研究大会
日時:2025年10月25日(土) 10:00〜18:00
場所:東京大学本郷キャンパス 国際学術総合研究棟1F 三番大教室
□ プログラム
10:00〜12:00 一般研究発表
新里喜宣 「「崔順実ゲート」と「第20代大統領選挙」における巫俗言説」
大沼巧 「朝鮮半島の海面における伝統的な権利・権益の特徴と日本統治後の変化について」
羅孟晋 「迂回としての「チプ」—グリーンハウスにおける家族と世帯の改編」
12:30〜13:00 会員総会
13:10〜18:00 シンポジウム「今また振り返るフィールド」
趣旨説明:林史樹
報告:平木實 「浅学児の韓国体験」
鶴園裕 「韓国留学時代—1970年代を中心に」
伊藤亜人 「フィールドワークと社会変化」
嶋陸奥彦 「予測と不測」
吉田光男 「現場を歩いた歴史学」
コメント:権香淑
鈴木文子
総合討論
18:30〜 懇親会 和食ごはんと酒 縁 本郷三丁目店
東京都文京区本郷7-2-12 スカラグリジアB1
電話050-5488-7558
□発表・報告要旨
(1)一般研究発表の要旨
新里喜宣 「「崔順実ゲート」と「第20代大統領選挙」における巫俗言説」
1945年の解放以降、巫俗は迷信として批判されながらも、同時に韓国文化の源泉として再評価の対象ともされてきた。たとえば、1970年代のセマウル運動においては大々的な迷信打破運動の一環として、全国で巫俗の儀礼の場所であるクッ堂が破壊されたが、一方で政府は民俗政策を推し進め、多くの巫俗儀礼が無形文化財に登録されるに至った。このような流れのもと、巫俗を肯定的に捉える視点が韓国社会でひろく共有されることとなる。報告者の見るところ、1980年代の社会浄化事業を最後に、巫俗を否定的に捉え、クッ堂の破壊にまで事が及ぶことはなくなった。以後、新聞や雑誌等のメディアに単発的に巫俗を否定的に捉える連載記事が掲載されることはあったが、巫俗に対して公的な批判が持続的に加えられることはなかったと考えられる。
しかし、2010年代後半より、突如として巫俗がメディアで露骨に批判され始める。2016年の「崔順実ゲート」がその発端である。当時の現職大統領・朴槿恵(敬称略、以下同様)を裏から操り、国政を壟断したと評価される核心人物として崔順実(本名:崔ソウォン)の存在が明るみに出たのである。これに怒った民衆のデモに触発され、2016年12月9日には国会で大統領弾劾訴追案が可決、2017年3月10日には憲法裁判所によって大統領の罷免が宣告された。この一連の事態・事件は崔順実ゲートと呼ばれるが、崔順実ゲートにおいて特に取り上げられたキーワードは「巫俗」であった。崔順実の父・崔太敏が小さな教団の指導者を名乗っていたこと、朴槿恵の様々な発言が巫俗的と捉えられたことにより、多様な角度から巫俗批判が提起された。
崔順実ゲートでは大統領弾劾にまで至ったが、その後巫俗批判は多少の小康状態に入る。そして、2021年から本格化する第20代大統領選挙において、再び巫俗は激しい攻撃にさらされることとなる。国民の力の候補選出における討論会で、2021年10月2日、尹錫悦候補の手のひらに「王」の字が書かれていたことが判明し、これが巫俗ではないか、との疑惑を呼び起こし、激しい巫俗批判の発端となった。以後、2022年3月9日の大統領選挙まで(そして2025年の現時点まで)、巫俗は常にメディアで否定的に扱われてきた。
本報告は、崔順実ゲートと第20代大統領選挙における巫俗言説を、巫俗言説の歴史的展開のもと捉えようとする試みである。これら二つの出来事において巫俗は、政治を裏から操る韓国社会の闇、なにか得体のしれない存在として言及された。しかしその一方で、じつに多くの媒体、主体が巫俗について語りつつも、前述したセマウル運動や社会浄化事業ほど踏み込んだ巫俗批判がなされなかったことも事実である。その意味を、とりわけ1960年代以降社会的に共有されることになる、巫俗を再評価する動きとの関連で捉えてみたい。
大沼巧 「朝鮮半島の海面における伝統的な権利・権益の特徴と日本統治後の変化について」
本報告は、近代移行期の朝鮮半島の海面における権利・権益の実態とその変遷について、地域の実態に沿って明らかにしたものである。これまでの韓国漁業史研究においては、日本人漁民の進出や日本人による漁場侵奪という観点から進められることが多く、韓国の海面が単なる侵奪対象とみられる傾向にあった。こうした研究は、日本統治期以来の朝鮮漁業に対する停滞的な見方や日本人による「開発」といった視点に対する批判的な視覚の必要性を考えれば、戦後の朝鮮史研究としては自然な流れだったといえよう。
しかし、実際には朝鮮時代以来、海面には明確な根拠のあるものから慣習的なものまでさまざまな権利・権益がすでに存在しており、それは日本が無視できるようなものではなかった。そのため、日本の朝鮮半島海面への進出とそれによって起こりうる朝鮮社会の変化は一様ではなく、具体的な事例を見ていく中で、その特徴を明らかにしていかなければならない。
本報告では、海面の権利・権益の全体像を意識しつつも、主に2つの事例に焦点を当てることにした。一つは、朝鮮時代以来漁業が盛んであった慶尚南道の事例である。同地域では、王室のかかわりや大韓帝国期の混乱、その後の日本の実業家の関与など、時代の変化に大きな影響を受けたという点で、海面の権利・権益の変化を考えるうえで示唆するところが大きい。もう一つは、朝鮮時代前期から塩業が盛んだった忠清道の事例である。同地域の塩業は、朝鮮時代に国家財政としての機能を期待されることもあったが、次第にその機能を失っていった。それでも、その後も王室の関与や地元民の努力により、少なからぬ利益を生み出すことがあったことも確認できる。ただし、塩業における権利・権益は、それほど重要なものとはみなされず、日本統治期には伝統的な権利・権益の存在を確認することは困難になっていた。
本報告では、こうした具体的な事例を紹介するとともに、現在までの研究の課題や今後の方向性についても示していきたい。
羅孟晋 「迂回としての「チプ」—グリーンハウスにおける家族と世帯の改編」
近年の韓国家族研究は、「脱家族主義」に焦点を当て、近代的概念装置としての「家族」の自明性に疑義を呈し、その構築過程と揺らぎを捉えてきた。本発表では、こうした議論を踏まえ、都市住民による農村への移住と就農(帰農)に着目し、生活と経営にまたがる多重的関係性を包摂する「チプ」の可塑性を再考することで、ポスト産業社会における家族・世帯実践の「迂回的」な性格を示唆する。ここでいう「迂回」とは、ジレンマに直面しても既存の環境や規範に正面から対抗せず、それらの両義的な複数の含意のあいだを行き来しながら、実践的判断によって条件や規範性を変容させていくダイナミクスを指す。
2010年代以降の帰農は、国家・地方行政による支援のもと、資本・技術の投入や外国人労働者の流入と交錯しつつ、小農生産を基盤とする農業自由化の枠組みに統合されていった。一方、「IMF危機」以降の中産層的核家族の一部は、自己搾取的家族労働と柔軟な生産様式(自営業や農業等)を接合することで、小規模家族経営体として再編されてきた。このような二重の転換のなか、帰農者と労働者が交差する農家世帯では、「家族」という関係性を媒介とするケアの倫理と権力関係が両義的に動員され、不安定な「チプ」が編成されている。
本発表でとりあげるイチゴ栽培は、小規模かつ高収益の経営形態として帰農者に選好されるが、温室施設内での不法居住や長時間労働が特徴でもある。こうした営農環境のもとでは、帰農をめぐる夫婦の交渉と核家族の再編が重要な論点となる。都市生活に挫折した夫による帰農の提案をめぐり、妻は都市残留か農村移住か、家事専従か農業への参与かの選択を迫られ、議論の末、世帯構成は夫の単身就農・温室居住、夫婦移住・温室居住、あるいは親子移住・市街地居住へと分岐する。一部では、子育てを終え農業教育を受けた妻が、農場経営に参入し夫の権威を相対化する試みも見られる。ここでは家族へのケアがそれぞれの行動の善き動機として語られる一方で、夫婦間の権力関係や願望には微細な変動が露呈している。
くわえて、共同労働や隣接居住を通じた外国人労働者との擬似的な親密性も際立つ。帰農者は彼ら彼女らを自己搾取的家族労働に取り込み、「情」や日常的な配慮を通じて農場への帰属意識を醸成しようとする。時には親しいコミュニケーションも行われるが、より良い条件を求めて夜逃げする労働者も少なくない。帰農者は、自らの家族のために働く労働者に同情を寄せる一方、「情」への裏切りを道徳的に非難し、一定の境界を保った相互依存的な関係性を模索している。
このように移動性と不確実性が高まる現代農業において、帰農者たちは、実践と規範を一義的に受け入れるのではなく、それらが孕む両義性のあいだを「迂回」しながら、「チプ」のあり方を再構成している。本発表は、こうした実践の動態に注目し、現代韓国家族研究に対して一つの解釈枠を提示したい。
□ (2)シンポジウム「今また振り返るフィールド」
韓国・朝鮮文化研究会は2000年10月に設立された。第1回研究大会シンポジウムは「交叉するフィールド」と題して開催され、続く第2回研究大会シンポジウムも「韓国におけるフィールドのあり方」と題されたように、設立当初から「フィールド」という用語で緩やかに捉えられるような実証的・経験的な調査研究の場が意識されてきた。しかし、その後、四半世紀が過ぎ、フィールドとして捉えられてきた研究者それぞれの研究の場も、また研究会を取り巻く環境も様変わりした。そこで今大会ではこのような変化にともなう研究対象や方法の変化を振り返ってみたい。
ただ、フィールド概念は、研究会内で必ずしも一致しているとは言い切れない。さしあたり、設立趣旨文には「現場を重視する研究」とあり、そこから考えると、フィールドとは、一義的に「現場」(たとえば各自の研究を構成するものが実際に生起する場)と置きかえられる。また特定の地域・地点や場所に焦点を合わせて「現地」という語で捉えることもできる。もちろん、フィールドとの距離の取り方やアプローチの仕方は研究分野によって異なってくるほか、朝鮮半島が南北に分断され、政治体制にも違いがあるため、フィールドの枠組みや意味するところも一定ではない。たとえば、従来の美学や音楽学、文学研究において、作品の鑑賞や読解の範囲であれば、研究者同士の交流や作品の原物に触れる以外の目的で、現場(現地)に足を運ぶ必要を感じないこともありえたかもしれない。また体制が異なる国家に分断された状況で、現場(現地)に足を運ぶこと自体が政治的メッセージと捉えられることもあり、歴史学などでは渡韓して研究すること自体が、慎重にならざるをえない時期もあった。
一方、フィールドを研究者とその研究者が調査・研究の過程で遭遇する他者や場所とのインタラクションを通じて生成される場と捉えれば、研究分野を問わず、研究者は日々の研究活動を通じて絶えずフィールドを生成し、更新しているともいる。すなわちフィールドは、その時々のインタラクションに応じて生成・変容する可変的な空間とも捉えられ、その意味ではすべての研究者が何らかのフィールドに身を置いていることになる。これを相互に対照することを通じて、それぞれの研究実践への省察を深めることが可能となろう。また本研究会会員の多くが現地の言語を駆使して研究を進めていることを考えれば、それぞれのフィールドを構成する現地・現場経験の重なり合いも決して小さくはないといえる。とくに現地調査を重視する民俗学や宗教学、社会学や人類学などの分野では、日韓国交正常化以降、比較的に早い時期から研究者が現地に足を運び始めたが、それだけに早くからフィールドの変化に対応が迫られてきたし、その対応から得られる視点は、研究分野を越えて広く共有できるものとなるだろう。
今大会では、初期に議論したフィールドに再び焦点をあてるが、絶えず変化をしてきた研究のかたちは、研究者がフィールドと向き合い始めた初期からどのような違いをみせてきたのか。少し遡るだけでも光州事件、ソウルオリンピック、アジア通貨危機、サッカー日韓W杯、韓流ブームといった出来事は、韓国社会に多大な影響を与えた。登壇者は研究歴の長い歴史学者と人類学者になるが、これまでフィールドで経験した変化を、その時々でどう受け止め、その変化にどう対処したのか。受け止め方や対処法は個人によっても研究分野によっても異なるが、この間のフィールドの変化とそれぞれが身を置く研究分野の研究環境や研究傾向の変化について多角的に振り返っていただく。
当会が標榜してきた「現場を重視する研究」の25年の歩みを、戦後日本の韓国・朝鮮研究の流れの中で捉え直し、韓国・朝鮮研究のフィールドをみつめ直す。さまざまな変化をどう捉え、対処し、研究を続けてきたのか、全体討論では学問分野の垣根を越え、登壇者の経験や知恵、模索を聞き、共有することで韓国・朝鮮研究のさらなる発展につなげたい。
(文責:林史樹)
報告題目
報告:
平木實 「浅学児の韓国体験」
私は1964年3月に留学したが、過去に日本の植民地支配を受けた当時の韓国では、日本に対する国民感情が非常に厳しく、ソウルでは日韓会談反対の集会や学生デモ、戒厳令を目の当たりにした。それをみて日本人としての責任が非常に重いという認識をもった。そうした体験は日本にいて報道で見聞するだけでは理解できない状況であったと考える。個人的には、朝鮮学科という当時の日本で唯一の学科を卒業したこと、中山正善・高橋亨教授を中心にして結成された朝鮮学会が組織されていて、その国際交流によって、韓国の大学関係者の好意を受けることができたように思う。また一般の人々も韓国文化を学びに来ているということで好意的に接してくださる人が多かった。韓国というフィールドで体験した様々な事象のなかで、つぎの二点に絞って報告したいと思う。
1.所謂倭色宗教の扱われ方について
当時の韓国社会では、倭色文化を排撃する必要があるとして、言語や歌謡界、映画界などの日本文化をはじめ、創価学会や天理教などの宗教団体がキリスト教、仏教などのような国際的な宗教でないとして強い行政指導を受けていた。天理教については、天理教の信奉する親神の神名のなかに、伊弉諾尊、伊邪那美尊などの天照大神の親にあたる神名を用いているとして不敬罪として教義の公開を許されず、明治時代の日本政府の宗教政策により弾圧を受けたりしていたが、韓国では、逆に韓国を植民地支配した日本の天皇の皇祖神を信奉している宗教団体であると批判されたり、創価学会は「韓国人の信徒も「南無妙法蓮華経」となにはばかることなく、日本語で念仏を唱えている創価学会は、日本仏教の一分派である日蓮宗を信じる信徒たちである。…日蓮が北条軍事政権の御用宗教家であったのと同様に日蓮宗は、東條軍事政権の忠実な御用宗教であったのである。といった理由で批判を受けていた。…」(「京郷新聞」1965年8月5日号)
2.ソウル大学校大学院史学科国史学専攻というフィールドにおける体験
ソウル大学校の大学院史学科国史学専攻碩学士課程に外国人学生として入学することが認められた。ソウル大学校のキャンパスは、東崇洞にあった旧京城帝国大学の校舎がそのまま使用されていた。研究を続けたい卒業生たちは、高等学校の教員などをしながら、ソウル大学校奎章閣の閲覧室に通い、小瓶に入れたキムチと麦飯弁当持参で貴重な文献資料に取り組んで研究にいそしんでいた。学生デモなどは無視して政治に関与せず学問に打ち込んでいた。韓国の若手研究者が熱心に研究に打ち込む姿に刺激を受けて、とくに才能があるわけでもない自分はもっとしっかり研究しないといけないと痛感した。当時のソウル大学校の若い歴史研究者たちは「なぜ韓国は日本の植民地支配を受けるようなことになったのか」という点について強い関心を抱き、それを究明するためには朝鮮時代後期の研究を推進する必要があり、社会経済史の研究、農業史の研究、「実学派」学者たちの研究を深めていく必要があるという傾向が強かったように思う。
鶴園裕 「韓国留学時代、1970年代を中心に」
1950年生まれの私が、韓国に留学したのは1974年から78年で、韓国は朴正熙(1917~79)軍事政権の末期であった。1972年には南北共同宣言(7月4日)が発表され、一方では10月維新を行って、軍事独裁体制が強化され、1973年には金大中拉致事件、74年春には民青学連事件が発生して、早川・立川の二人の日本人が逮捕され、韓国の刑務所に収監されていた。同年8月15日の光復節に日本が支援したソウル地下鉄が開業した同じ日に、在日コリアンの文世光による朴正熙狙撃事件が発生し、陸英修大統領夫人が死去した。
このような時代を背景に、私は1974年4月に観光VISAで韓国に入国し、韓国の延世大学校の韓国語学堂で韓国語の勉強をしていた。当時は観光ビザで入国しても3か月の短期留学ビザに切り替えが可能であると言われていたからである。しかし、前述のような時代背景の為に再度正式な留学生ビザの取得が必要であるとされ、日本への一時帰国が必要であると言われた。VISAの相互主義という理由であった。2か月程度で許可がおりるであろうと言われたが、正式な留学生資格のVISAが下りたのは文世光事件後の8月31日であった。
半ばあきらめかけていた韓国留学を再開したのは9月11日からであり、その後も6級までの韓国語学堂の正式のコースを終えて、75年秋には延世大学校の文科大学院、韓国史学科の碩士過程(日本の修士課程に当たる)に入学する事になる。
その後の3年間の金容燮教授の指導による大学院の学生生活は、楽しくも厳しいものであったが、今回のレジュメでは字数の制限もあるので、朝鮮史という歴史学と文化人類学という事のフィールドの共通性と違いという様な事を意識しながら、シンポジウムでは報告したいと思う。時間があれば、地下鉄における席を譲る作法の消失や、保身湯(ポシンタン、犬肉食)とクジラ肉食ではどちらが伝統食として生き残るか、葬礼における土葬から火葬への変遷の問題なども歴史学や文化人類学の立場から論じてみたい。
(参考文献)
鶴園裕、1995「朝鮮史研究と文化人類学」『金沢大学教養部論集・人文科学編32』
原武史、2025「9年ぶりのソウル地下鉄」『歴史のダイヤグラム』朝日新聞7月5日(土) be on Saturday
原武史、1996『直訴と王権、朝鮮・日本の一君万民思想史』朝日新聞社
平木實、2019「朝鮮学と私」『朝鮮学報』251
油谷幸利、2025「私と朝鮮学—油谷幸利先生に聞く—」『朝鮮学報』265
カーター・J・エッカート(松谷基和訳)、2024『韓国軍事主義の起源 青年朴正熙と日本陸軍』慶應義塾大学出版会
伊藤亜人 「フィールドワークと社会変化」
韓国・朝鮮社会を研究対象とする研究者の間でも、現地社会あるいは人々との関わりのあり方は様々である。現地研究の中でも人類学が提唱してきたフィールドワークは、研究者が自ら現地社会に身を置き、自身の観察と洞察に基づき記述をするもので、事例研究を通して人間社会の一般化に寄与するという展望に立っていた。研究者も対象も個別であって、両者の関係も個性や相性に大きく依存するものだった。私自身が1965年に進学した東京大学の文化人類学教室は、学科設置の段階から米国の影響のもとで、泉靖一教授の積極的な発信によって「人間の総体的研究」という理念を掲げて、とりわけフィールドワークという新鮮な手法が注目を惹いた。
本企画は、フィールド社会の変化に注目して、研究者の側の経験と展望を共有することが趣旨と理解している。人類学ではかつては主として未開社会を対象とした共時的な研究姿勢が重視され、通時的な観察記述とか動態的研究が提唱されてはいても社会変化研究が主流とはなりえなかった。歴史は背景として記され、記憶や記録や遺物などを通して社会変化を記述するに留まっていた。今日では、人類学自身が近現代の社会変化の中で立ち位置を自覚するようになったが、もともと社会は常に変化するものであり、研究者の社会性も認識も変わり、両者は相互性のもとで生成するものである。また研究と開発(介入と変化)を一体化させて積極的に社会変化に関与する試み(Research and Development, Participatory Development)は開発研究の主流をなしてきた。
以下に自分の経験をもとに、共有できると思われる点を思いつくまま挙げておく。
・文化人類学におけるフィールドワークの位置づけ。人類学の研究者として必須かつ通過儀礼といえる位置づけ。異文化に身を置いておこなう全人格的かつ知的な試みであり、人文社会学の中でも斬新かつ魅力的な経験として評価。
・未開社会を想定した静態的なフィールド像。個人が直接観察・記述できる小さくてシンプルな社会単位に対象を設定。総体的(holistic)な観察・記述を意識。
・農民社会や町社会などの複雑社会complex societyにもフィールドワークの手法が試みられたが、日本では大幅に遅れていた。
・東アジア文明圏に対しては大伝統の文献資料と専門性の壁 (歴史、思想、宗教)を避ける傾向。帝国主義との関連を忌避する消極性。日本研究を研究対象とする展望も遅れた。
・日本の漁村・家船の調査(1966~1969):差別に起因する困難。藩政時代の特権と御役、漁村社会の変動・流動性と社会経済史的研究への関心。
・五島福江の農村での体験(1969~1971):経済と行政、技術導入、開発をめぐる農村社会の課題への関心。Anthropology of Development。
・珍島農村での現地調査(1972~)。総体的な研究理念と長期的展望。静態的な印象と植民地期〜地方振興、開発独裁国民化(セマウル運動・国民経済)に伴う社会変動。物質文化・生態学的・経済的な変化。眼前の農村生活の記述を優先し、歴史については手遅れ。
・人口流動、過疎化と老齢化、機械化と労働慣行の変容。チプの形骸化、門中の再編、祭祀と墓地、農村の教育、多文化家庭、外国人労働者、老人と貧困、地域消滅の危機、珍島学会、異邦人・研究者の経験。
嶋陸奥彦 「予測と不測」
私が初めて韓国で現地調査を行ったのは1974年8月から一年間、全羅南道羅州郡の農村で、家族・親族組織、村落組織、農業活動などを中心とするものだった。
二度目の調査は1980年と81年の夏に慶尚北道星州郡の農村で、全羅南道との地域差を確認しようという目的だったが、この時に一つの親族組織の族譜をゆっくり見せてもらうことになった。注目したのは、歴史のなかで一族の人々が全国各地に移住して居住するようになっているという実態であった。
国立中央図書館でその一族の族譜をコピーし、それによって一族の人々の現住地を確認することができた。それをもとに、82年の夏に全羅北道、忠清南北道、慶尚北道の村々を訪問したが、この調査を通じて、編纂時期のことなる五つの族譜を入手することになった。
これらの族譜を比較すると、時代が下るにつれて系譜が長くなるだけでなく、版によって新しく記録されるようになる分派がある一方で、記録されなくなる分派もあることが分かった。そこから見えてきたのは族譜編纂に関与した全国各地の子孫たちの関与の歴史だった。これを契機に私自身の関心も親族組織の歴史過程へと広がることになった。
1986年秋から一年間、ハーバード大学で研究する機会を得た。そのとき出会ったのが朝鮮時代の大丘戸籍である。その分析を通して、17世紀末から19世紀中期にわたって形成されてゆくいくつかの親族集団の存在を確認した。
1996年から98年にかけて、これらの親族組織の現状を確認するための現地調査を行った。そのとき目撃したのが、大邱市街の拡大に巻き込まれた親族集団の対応であった。特に目をひかれたのが市街地にとりこまれた墓地の移転問題だった。
大邱市での都市化現象の調査をしていた時に、以前に星州郡での調査のときに世話になった門中の宗家の主人と偶然にも再会することになった。そこで知ったのは、農村の宗家の奥さんが大邱市街地の露天商街で露天商をしているということだった。
これをきっかけに、2000年から2003年にかけて、大邱市達西区の露天商街の調査をすることになった。これが私にとっての最後の本格的現地調査ということになった。
自分の研究史を振り返ると、それは予測もしなかった事態との出会いの繰り返しであった。
吉田光男 「現場を歩いた歴史学」
「交差するフィールド」という本研究会の趣旨に立ち返って、1970年代以降の、朝鮮近世史研究という専門分野(フィールド)と、朝鮮半島という事象生起空間(フィールド)の二つのフィールドで、どのような活動を行ってきたのか振り返ってみる。
私がその中に身を置いてきた1970年代以降の、日本における朝鮮近世史研究の動きは、おおよそ以下のように概観できる。
①1970年代(黎明期)。文献資料による研究のみだったが、ようやく韓国現地に目が向けられるようになる。少数の先達が韓国に入り始めた。朝鮮近世史研究者の現地入りが遅くなったのは、朝鮮近世史に対する関心が薄く、そもそも研究者自体が僅少であったからである。近世史研究はほとんど田川孝三氏(『李朝貢納制の研究』、東洋文庫、1964年)という孤塁によって細々と行われている状態であった。朝鮮史に対する研究的関心は、古代史と近代史、それも日本との関係に集中しており、近世史は大学でもほとんど教育が行われていなかった。
②1980年代(助走期)。ようやく近世史(李朝史)の研究者が育ち始め、1981年10月に朝鮮史研究会大会で「李朝史の諸問題」をテーマにしたシンポジウム開催にこぎ着けたが、内容はさておいて「初めて近世史シンポジウムができたこと」が評価される状態であった。
一方で、少数の研究者による現地回りが始まる。吉田の場合、この時期に、嶺南、湖南を中心にしてマウルタニギを繰り返した。安東川前里義城金氏、安東西後面鶴峯宗家、奉化酉谷里安東権氏、礼安下渓里李退渓故家、海南尹氏(尹善道宗家)など、宗家と集姓村を回る。一方ソウルでは、17〜19世紀の古地図と地籍図などによる街路調査、戸籍台帳による街区調査を継続する(『近世ソウル年社会研究』、草風館、2009年)。その多くは、再開発計画によって21世紀になって湮滅してしまった。
③1990年代(号砲)。吉田が全国の若手研究者や大学院生を連れて、意識的な「現場回り」を行う。各道の近世史関係「現場」(集姓村、宗家、書院など)をひたすら回り、住民の聞き取りを行う。目的は、現地感と現場感の養成、人々とのつきあい方の訓練、そして何よりも、近世の残り香を「経験」すること。この時に訪問した集姓村や宗家の多くがその後急速に変容し、オルシンの別世、過疎化、集落の観光地化などで「近世の残り香」が失われてしまった。
本シンポジウムでは、このような1970年代から現在までの朝鮮近世史研究が、「現場」とどのように取り組んできたのかについて、自分の「経験」を中心にして話題を提供し、「経験」の意味を議論したい。
以上
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内