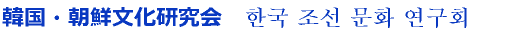![]()
第13回大会
日 時 : 2012年10月27日(土) 10:00~17:30
場 所 : 東京藝術大学音楽学部(上野キャンパス)5号館5-109号室
上野キャンパスへのアクセス→(http://www.geidai.ac.jp/access/ueno.html
なお、学内と近辺に食事のできるところはございませんので、昼食は持参されることをお勧めします。)
□ プログラム:
10:00~12:00 一般研究発表(1)
文聖姫「北朝鮮における社会主義計画経済と市場化の融合の可能性」
中尾道子「東京藝術大学附属図書館蔵『中枢府重修宴契会図』の絵画史的位置」
崔蘭英「領選使派遣から見る1880年代初頭における朝鮮と清との交渉」
12:30~13:00 会員総会
13:10~13:50 一般研究発表(2)
神野知恵「農楽の『クッ文化』の伝承と再創造:高敞農楽伝授館と学生サークルにおける2006年からの参与研究」
14:00~17:30 シンポジウム「アリランをめぐる音・ことば・語り」(企画:植村幸生、司会:野村伸一)
研究報告
植村幸生「〈アリラン〉の複数性:統合と葛藤」
山内文登「東アジアの上演的近代とアリランの位相:音声・翻訳・媒体」(仮題)
林慶花「忘れられた冷戦下の〈アリラン〉」
植村幸生「五木の子守唄とアリラン」
総合討論
18:00~20:00 懇親会(会場:大学美術館(美術学部)内、大浦食堂)
□ 発表・報告要旨
(1)一般研究発表
■文聖姫「北朝鮮における社会主義計画経済と市場化の融合の可能性」
1990年代後半の「苦難の行軍」の過程で、北朝鮮では闇市であるチャンマダンが表面化した。人々は工場や企業所に出ても賃金を得ることができないため、チャンマダンに出て各々自宅で作ったパンや麺類などを売る小規模な商売で日銭を稼ぐようになった。この過程で、自力で生きていくことの出来ない人たちは自然淘汰された。現存する人々はそういう過程を自力で生き抜いた人たちである。しかも、闇市の表面化を統制できなくなった政府が2002年にこの現象を「追認」する形で一連の社会主義経済管理改善措置を実施する。この措置に基づき農民市場は2003年に工業製品も販売可能な総合市場として運営され始めた。
だが、それにはあくまで「社会主義の原則を守る」という前提がついていた。金正日は2001年10月3日の談話「強盛大国建設の要求に合わせ社会主義経済の管理を改善強化することについて」で実利に沿って経済管理改善を行うべきだとした。その後の2002年から一連の経済改革措置が断行されたことを見ると、金正日がこの時期、経済改革路線に舵を切ったのは確かだったが、2005年以降、市場経済化が進むことを懸念した北朝鮮当局は経済管理改善措置を後退させる。総合市場ではなく、国営商店に国産品を供給し国定価格で人民に供給する従来の方式を回復させる方向を目指す。国営商店に物が十分に供給されるようになれば、総合市場は将来的にはなくしていく方向であるが、国営商店にまだ物が十分に供給されない状況だ。その要因としてはエネルギー不足による工場稼働の停滞、外貨不足によって原材料を十分に獲得できないことなどが考えられる。
それでも、国営商店に品物を供給しようとする努力がある程度功を奏してきているのは確かだ。平壌第一百貨店には国産の品物が並ぶ。もちろん、外国産の物も売っており、国産の物は外国産の物に比べて見劣りがするのは確かだが、その分安価だ。平壌ではコメの供給が復活するなど、社会主義計画経済態勢に戻すための努力は続けられているようだ。こうした事実は、社会主義計画経済路線は維持するという当局の意志の表れだといえる。
一方、北朝鮮の人々は1990年代末から2000年までの建国以来最大の危機時期を乗り越えたが、それは結局、人民も企業も自分の生活は自力で解決するとことを学ぶ過程でもあった。その過程で、国家の思惑に反してチャンマダンや総合市場の力が巨大化、人々は市場なしでは生きていけない構造が生まれた。総合市場で物を買うためには、給料以上の現金が必要になる。人々は国家に頼るのではなく、商売や副業をすることで、自力で生活費を稼ぐ道を模索している。これは下から市場経済化が進展していることを示すものだ。
本発表では、2010年から2012年までの北朝鮮での現地調査をもとに、社会主義計画経済と市場経済の融合の可能性について探ることを目的とする。
■中尾道子「東京藝術大学附属図書館蔵『中枢府重修宴契会図』の絵画史的位置」
東京藝術大学附属図書館に「樂舞図」(貴重書768.9/G47-9)の名で蔵される絹本軸装の一幅は、楽舞を伴う士大夫官僚たちの宴の様が描かれた中段の画を挟んで、最上段に篆書で「中枢府重修宴契会図」と記された標題とその下の草書体の賛詩、下段に参会者の座目を備えた契会図と称される記録画の一種である。
契会図とは朝鮮時代前期から中期にかけて流行した絵画形式で、その典型的な形式は竪長の画面の最上段に、右から左に絵の標題、つまり契会の名称が篆書体で記され、その下の中段に契会の場面が描かれ、下段に契会の参会者たちの姓名・字・本貫・生年・位階・父親の名などを記した座目が配されるというものである。本図はその契会図の典型的な形式をとる絵画であり、現在知られる作例の中では比較的大幅に類するものである。伝世する契会図には制作時期の手がかりとなる標題や座目部分が鑑賞形態に合わせて切り取られたと考えられるものも少なくない。幸い本図は参会者十四名の座目を備え、また標題下に賦された賛詩末尾の「萬暦戊子燈夕」により、明萬暦16年、すなわち1588(宣祖21)年4月ごろの制作と推定することができ、現存する作品が少ない壬辰倭乱以前の朝鮮絵画の貴重な作例であるといえる。
現存する契会図は十六世紀以降のものであり、中でも十六〜十七世紀に際立って作例が多いことは作品・文献の双方から認められる。十六世紀前半では、「読書堂契会図」(日本・個人蔵)や「司饔院契会図」(日本・個人蔵)のように契会場面は点景として描かれ、背景であるはずの山水を主体とする構成を見せている。ところが、十六世紀半ばになると「戸曹郎官契会図」(国立中央博物館蔵)のように人物を中心にした作例が現れ、次第に本図同様、屋内での契会場面が詳細に描かれるようになる。本発表では、「中枢府重修宴契会図」の図像を検討し、特に本図と近い時期に制作された他の契会図の緒作例との比較を行い、その表現形式を分析することによって、本図の朝鮮絵画史における位置を考察する。
なお本図は明楽関連コレクションの一つとして分類され、近年までほとんど注目されることなく韓国の学界にも知られてこなかったが、植村幸生氏が音楽史の立場から東洋音楽学会第61回大会(「東京芸大図書館蔵「中枢府重修宴契会図」にみる十六世紀世紀朝鮮の宴礼楽舞」2010.11.14東京学芸大学)において紹介されており、本図の来歴および成立時の事情、描かれた楽工や楽器、楽舞の形態について検討されている。しかしながらいまだ美術史学的検討が行われていないため、本年6月に行った作品調査を踏まえ、本発表に際し、その絵画史的位置について若干の知見を加えつつ考察を試みたい。
■崔蘭英「領選使派遣から見る1880年代初頭における朝鮮と清との交渉」
1881年10月に、朝鮮は兵器・機械の製造技術を学習するために、清国へ留学生と工匠(軍械学造団)を派遣した。引率する領選使金允植一行はこれを機に、清の李鴻章を介して米国との条約交渉にかかわり、「朝米修好通商条約」の締結につながった。 領選使の清国派遣は、日本への紳士遊覧団派遣と並んで、朝鮮が近代的科学技術を受容・導入する重要な契機になったと高く評価される。一方、留学生・工匠は予期の成果を果たせず、技術を身につけることなく一年で帰国してしまったことから、領選使の派遣を「失敗」したと否定的に見られている。その原因は不適切な人選、財政支援の不足、壬午軍乱による混乱、および軍乱鎮圧後に清の対朝鮮政策の転換などにあると指摘される。
既存の研究は留学生の学習成果の有無とその後清軍の朝鮮駐屯など外的要素に注目する余り、朝鮮が自ら兵器製造できるようになる貴重な機会を逃したとの結論まで導いている。
本報告では、こういった問題点を指摘する既存の研究と異なる視点に立ち、領選使派遣の背景を再検討し、同時代の朝鮮の政治家の言動を分析することにしている。
1880年代に入って、朝鮮は「武備自強」を目指したものの、当初は兵器の購入を急務にしていた。ところが、他国(専ら日本)を通しての購入は、清との関係に切れ目を作ってしまう恐れがあった。また、資金の調達も一つの難題であった。これらを如何に解決していくかが朝鮮の課題であった。
報告では、清と交渉する朝鮮の政治家が目指したものを明らかにして、その交渉の手法に注目したいと思う。朝鮮は如何に清を味方にし、相互の関係を円滑にしていくかを軸に、卞元圭と游智開、魚允中と唐景星、および金允植など諸政治家の交友関係を分析して、同時代朝鮮と清の官僚たちの人的ネットワークの一角を描き出すことを目標の一つにしている。朝鮮と清との間の「宗属関係」、または属国でありながら「自主」を主張していくという従来の描き方から異なる部分が見られたら幸いに思う。
■神野知恵「農楽の『クッ文化』の伝承と再創造:高敞農楽伝授館と学生サークルにおける2006年からの参与研究」
朝鮮半島南部に伝わる芸能「農楽(プンムルクッ)」は、体系的研究が困難な分野であると言える。その理由のひとつは、一言で「農楽」と言っても、個々の事例があまりにも多様なコンテクストを持っているからである。地域によって、行われる機会、規模、演奏者の身分、芸の内容や複雑さが異なるため、「農楽とは」という全体的な定義はそもそも不可能に近い。さらに、時代の急激な変化に伴って各々のコンテクストが大きく変化し続けているため、農楽が韓国・朝鮮文化にとってどういった意味を持つのかという議論は難しくなる一方である。儀礼の芸能としての農楽は現代韓国人にとって、もはや過去の記憶であり、1980年代頃まで農村で十分に見られた光景の大部分が見られなくなっている。
しかし一方で、農楽は1990年代生まれの大学生たちをも未だに魅了し続けている。筆者は2006年から現在に至るまで、大学生農楽サークルの強化合宿に通い続けてきた。今日でも多くの大学生がサークルに加入し、地方にある伝習施設に通っている。特に、高敞農楽伝授館(全羅北道高敞郡)においては、プロ奏者である若手の講師たちと、その元に通う大学生たちによる活発な伝承が見られる。筆者は、彼らが農楽の何に魅了され、何に価値を置いているのかを観察してきた。人々が農楽に求める価値観は今後も急速に変化し続けることが予想され、この芸能の全体像を捉えるためには、現在(2000~2010年代)の記録をつけていくことも、今後重要な作業になると考えている。
今回は、伝授館で好んで用いられている「クッ」という概念について注目する。伝授館講師たちが学生を指導する際にこの言葉を積極的に使っており、その姿を見て学ぶ学生たちもこれに従っている。例えば、農楽の演奏を行うことを「クッを打つ」と言い、農楽の公演を見に行くことを「クッを見に行く」、さらには「クッシム(クッの心)」「クッ的なマインド」などという表現も用いる。もちろん、高敞をはじめとする全羅道地域では農楽による村落の祭儀のことを「クッ」と呼んできたため、この慣習を守っているとも理解できる。しかしそれ以上に、「演奏」や「公演」などの近代的概念ではなく、「クッ」という人間味のある伝統的な概念を用いることで、その言葉に含まれる美的価値観を大切にしようという強い意志が伝わってくる。何よりも、人と人との強い関係性や共同体意識を重視し、即興的で会話のような打楽器音楽を通じて、互いに共感し合うというところに、その価値観が置かれていると言える。
今回の発表では、高敞農楽伝授館の教育システムの変遷と現状を紹介した上で、「クッ」の文化を、若手講師たちがどのように受け止め、それを学生たちに伝えようとしているか、また学生たちがどのように受け止めているか、ということについて論じる。
(2)シンポジウム「アリランをめぐる音・ことば・語り」
■植村幸生「趣旨説明」
〈アリラン〉はこれまで、第一に「伝統的」な「民謡」として、第二に植民地時代の抵抗歌謡として、そして第三に民族統合の象徴として意味づけられ、語られてきた。これに、主として日本人によって語られてきた植民地主義的「悲哀民族」イメージ、在外韓国・朝鮮人による「望郷」イメージを加えることもできよう。
それらの意味づけが作り上げるイメージを仮に「アリラン像」と呼ぶなら、音楽としての〈アリラン〉の(再)創作、演奏、消費、教育、研究といった営みはつねに、〈アリラン〉像に支配され、とりまかれるように存在してきたといえる。このことが、〈アリラン〉を世界的にもユニークな「民族の歌」として広く知らしめる一方で、〈アリラン〉研究だけが突出した独自のジャンルを形成するかたちで個別に議論されるという、一種いびつな研究状況をもたらしてもいる。
このシンポジウムでは、従来の「アリラン像」の相対化をこころざす視点から、〈アリラン〉研究の現状と課題を振り返り、たとえば次のような論点を示しながら、今後の〈アリラン〉研究の可能性を展望したい。
1) 〈アリラン〉は「民謡」ではないのか:「民謡」概念の創出、民俗世界と〈アリラン〉の関係
2) 音のレヴェルにおける〈アリラン〉の上演様態:声のクオリティ、伴奏と和声づけ、ジェンダーなど
3) 〈アリラン〉歌唱の社会教育的側面:学校教育、うたごえ運動、アリラン祝祭、応援ソング
4) 日本における〈アリラン〉:翻案歌謡、公演活動、識者の言説
5) レコード、放送メディア上のコンテンツとしての〈アリラン〉
6) 〈アリラン〉の視覚表象:映画「アリラン」、レコードジャケット
■植村幸生「〈アリラン〉の複数性:統合と葛藤」
■山内文登「東アジアの上演的近代とアリランの位相―翻訳・媒体・音声―」
近年、東アジアの近代をめぐって翻訳が果たした甚大な媒介的役割の解明が進んでいる。国際法の翻訳と受容を介した中華秩序の再編と東アジア地域の誕生、「漢字文化圏」などと呼ばれる当該地域における近代的概念の漢訳語彙の量産と流通、そうした汎地域的な磁場における日朝中の文脈依存的な特性と差異、近世以前からの「訓読」の多様な実践との歴史的連続性・断絶性など、考察すべき論点は多い。これはまた、翻訳された概念や知識を記録し伝播する媒体とその現実構成的な機能への関心とも連関している。こうした研究は、理念的な近代の「起源」を不可視にしつつその東アジア的な編成を可能にした主要な媒介過程・作用(mediation)の「不透明さ」を改めて浮き彫りにするものといえる。
本報告の問題意識は、以上のような大枠において言語モデルに則った東アジア近代の論議に対して、音声という主題を切り口にその射程と限界をあぶりだし、アリランを事例としてより具体的に考察を進めるところにある。その一つの出発点は、音声の翻訳不可能性と呼びうる特徴である。すなわち、翻訳とは言語間における意味の等価性(equivalence)の担保を目的とした音声変換であり、逆に言えば概念の翻訳は音声の等価性を犠牲にすることで成立する。報告者は、この翻訳における音声の非等価性が、東アジアの近代音楽史のみならず、当該地域の近代経験一般を考察する上で極めて大きな示唆を与えると考えている。例えば、東アジアの音楽の近代における重要な一起点とされるのは翻訳の対応物、すなわち西洋の楽曲の替歌だが、それは歌詞に関わる実践であって、非互換的な音楽の部分は透明な媒体として大枠において温存され、流用された。こうした音楽的近代の胎動のあり方は、東アジアにおけるいわゆる西洋音楽の可聴的なプレゼンスとその絶大なヘゲモニー、それに媒介された地域規模の音楽的共役性の増幅などの問題を考える上で極めて重要である。それと同時に、当該地域における極めて多様な音声の文化が、翻訳的近代において流布した多種多様な概念装置に取り込まれ意味づけられつつも、音声それ自体としては単純に包摂されずに独自の展開をとげてきた点も看過できない。
以上の問題に加えて、本報告のもう一つの論点は、音声の複製技術の登場により、聴覚が他の感覚と切り離されてそれ固有の媒体を得たという事実である。録音技術は、近代科学思想において究極の「表音文字」として構想されたが、それは当初の書記性の領域を超え、それ自身の口承性・聴覚性の領域を構成し、また視覚と同期された視聴覚媒体の世界を切り開いた。東アジアの近代において、身体性や直接性を特徴とする音声の媒体が、新たな大衆文化の形成を可能にし、また大衆動員の契機をもたらした点も重要な論点である。
本報告では、以上のような問題系を軸として、19世紀末から20世紀前半までのアリランをめぐる以下のような問いについて時間の許す限り考えてみたい。19世紀末のアリランと五線譜や録音という異なる記録媒体との出会いとその後の展開の諸相、同時期にネーションをめぐる諸観念を翻訳・流布した文字・印刷媒体やそれを通じて伝播した数多くの「愛国歌」とアリランとの関係性、いわゆる「本調」アリランの生成と西洋音楽の介在性、帝国日本の大衆音楽形成とアリランの通文化的な受容や流用、アリランをめぐる替歌の実践や著作権等の所有観念の問題、出版警察の概念統制とその音声の検閲をめぐるアリランの位相、戦時体制や革命運動の理念的動員とアリランの経験などである。東アジアの音声・音楽の近代は、通常それらと様々な概念との従属的な相関性、すなわち国家、国民、民族、民俗、伝統、文化、文明、植民などの翻訳された諸概念に対する従属変数として考察される。本報告の狙いは、東アジアの近代における翻訳不可能または極めて困難な領域(これを仮に「上演的近代」という用語で呼ぶ)からその近代経験をめぐる諸問題を捉え返してみた場合に何が聴こえてくるか、といった方法論的問いを省察することである。
■林慶花「忘れられた冷戦下の〈アリラン〉」
〈アリラン〉は民族統合の象徴とされているが、享受の歴史を辿ると、〈アリラン〉は①その価値は一定ではなく、民族の歌としての価値が強調され始めたのは近代以降、正確には二十年代以降であり、②享受の範囲も朝鮮「民族」や朝鮮半島に限定されていたわけではないし、③そのイメージも「一つの民族」を幻想している点では一致していたにせよ、そこに投影された民族のあり方や歴史像は必ずしも均質ではなかった。つまり、「民謡」に対する左右異なる認識がそこにはあった。こうした対立は既に植民地時代に芽生え、解放後の体制の二分によって決定的なものになり、東アジアに広まった〈アリラン〉もそれに連動する形で享受されるようになった。〈アリラン〉の均質性を主張することは、〈アリラン〉の多様なあり方への抑圧になりかねない。そのため、本稿では〈アリラン〉の多様性、特に冷戦期にそれぞれの陣営によって築き上げられた〈アリラン〉の享受史に注目し、多様な〈アリラン〉を復元し強調することにより、現在の〈アリラン〉のイメージ構築に再考を迫りたいと思う。
■植村幸生「五木の子守唄とアリラン」
韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内